霧筑波誕生の原点は「出羽桜研修」 浦里酒造店、小川酵母にこだわり 連載「農大酵母の酒蔵を訪ねて」第14回 稲田宗一郎 作家
2023.06.01

JR常磐線の取手で関東鉄道に乗り換え、宗道駅からタクシーで浦里酒造店に向かった。浦里酒造店(茨城県つくば市)は1877(明治10)年に、茨城県結城市にある浦里(うらさと)本家の結城酒造から分家し、初代浦里(うらざと)新造によって旧吉沼村で創業された蔵だ。
事務所に挨拶した後、6代目の浦里知可良氏に取材をした。知可良氏は「令和2酒造年度 第102回南部杜氏自醸清酒鑑評会」吟醸酒の部で、史上最年少で首席を獲得した新進気鋭の若手杜氏だ。
挨拶も早々に、知可良氏の父で現代表の5代目浩司氏が1985年に、普通酒の生産から「純米酒」や「大吟醸酒」などに分類される特定名称酒の生産へと転換した背景を質問した。
知可良氏は「醸造試験所(東京都北区)で研修中に、出羽桜酒造の仲野益美さんと一緒だったことが、5代目の酒造りの原点だった」と、当時のエピソードを語ってくれた。

(5代目 浦里浩司氏)
<5代目と仲野益美氏は年齢も近かった。益美氏から影響を受けた5代目は、86年1月から2か月間、山形県天童市の出羽桜酒造で研修した。この研修が全国各地の酒蔵の後継者を研修生として受け入れる「出羽桜研修」の始まりだった。浦里浩司氏が出羽桜の初代研修生だったのだ>
出羽桜は75年に低温貯蔵蔵を建て、80年に「桜花吟醸酒」を発売、82年には生酒・長期熟成酒を発売しており、吟醸酒ブームの火付け役となっていた。この時の経験が、普通酒から特定名称酒「霧筑波」への生産転換を5代目に決断させた。
霧筑波を発売した85年に開店した西武百貨店筑波店は、当初から浦里酒造店の酒を取り扱った。地元つくばの酒として霧筑波が並び、都市部などから筑波学園都市へ移住してきた多くの人が、筑波の地酒として「霧筑波」を評価した。
霧筑波のラベルは、洋画家で芸術院会員だった服部正一郎氏の作品「霧筑波」を同氏の好意で使っており、作品名も商標として使っている。

(服部正一郎画伯の「霧筑波」のラベル)
5代目のこだわり「小川酵母」
「5代目の酒造りの基本は何でしたか」と6代目に尋ねると、「酒本来の香味を大事にした、昔からの仕込みから醸しだされる穏やかな風味。おいしいものを食べながらまた一杯、もう一杯と飲みたくなる酒」と答え、そんな霧筑波の味を決定付ける重要な要素として、「5代目は小川酵母という酵母に強いこだわりを持っている」と語ってくれた。
筆者は「小川酵母ですか」と驚いて聞き返した。小川酵母は水戸市の明利酒類に勤務していた小川知可良氏が、仙台国税局鑑定室長時代の1951年から52年にかけて、東北6県の数百という蔵のもろみから集めた内の1つの酵母である。
その酵母を発見した小川博士を師と仰いでいたのが、出羽桜の3代目仲野清次郎氏なのだ。3代目清次郎氏が初めて、出羽桜の吟醸酒に小川酵母を使ったのだ。
この話を伝えたところ、6代目は大きくうなずいた。6代目によると、小川酵母は香りが良く、酸が少なく、また低温でよく発酵するため、吟醸酒造りに向いている。
その優れた特色から、日本醸造協会が全国の酒蔵に醸造用として頒布するきょうかい酵母(日本醸造協会登録10号酵母)としても登録・培養されているが、浦里酒造店はその生みの親・明利酒類から小川酵母を分けてもらい、仕込みに使用しているとのことだった。
5代目がこの小川酵母にいかに惚れ込んだのかは、長男の6代目に「知可良」と名付けたことからも分かる。筆者はこの話を聞いた時に、出羽桜の3代目が「自分の酒造りの原点は信州『真澄』であり、酒造りの師匠は窪田千里杜氏、酒哲学の師は宮坂勝氏」と語り、息子である4代目に益美(ますみ)と名付けたエピソードを思い出した。
<この話を知っていた5代目は、小川博士の名前の知可良を自分の息子に付けたのだ>
この話を6代目にしたら、6代目は少し考えて「そうかもしれない」とうなずいた。
「低温貯蔵」と「氷点下熟成」
浦里酒造店には貯蔵庫の他にたくさんの冷蔵コンテナがあり、仕込蔵の内部はオールステンレス製で夏でも5℃以下に保たれている。さらに配送時の温度管理を徹底するため、20数年前に配送用の冷蔵車も購入し、1995年には低温貯蔵に加え、氷点下熟成が可能な蔵を新設した。
マイナス5℃の環境下で貯蔵できる氷点下熟成は、酒を氷点下でゆっくり熟成させる。アルコール添加をした吟醸酒は、搾りたてほどアルコールと酒はなじんでいないが、氷点下でゆっくり寝かせることでアルコールが一体化し、酒にまるみがでるのである。
この低温貯蔵や氷点下熟成の導入も、5代目が出羽桜での研修中に、4代目仲野益美氏との真摯な酒造りの議論から生まれたものだと筆者は思った。
5代目は30年前から、茨城県下妻市の農家と契約栽培している酒造好適米を使用した酒造りに取り組み、近年では「地元の米と材料で造る酒が終着点」と捉え、蔵のあるつくば市吉沼の農家と酒米の栽培に取り組み「霧筑波 吉沼米」を発売している。
「地元の食堂で売れる酒1本と、海外の三ツ星レストランで売れる1本。どちらも同じ1本だとしたら、ずっと地域の人が買ってくれている、そんな地元で売りたい」との5代目の言葉が心に残った。
連載「農大酵母の酒蔵を訪ねて」は、稲田宗一郎さんが国内で唯一、醸造科学科を持つ東京農業大学が生んだ酵母をテーマに、全国の酒蔵を巡るルポです。次回は6月15日に掲載します。
第1回:ダム堤脇のトンネルで熟成 「八ッ場の風」は華やかな香り
第2回:吟醸酒ブームここから 出羽桜酒造、歴代蔵元の挑戦
第3回:吟醸の魅力、世界へ 出羽桜、業界底上げ目指す
第4回:コメへのこだわりと挑戦 4社統合の伝統、宮城・一ノ蔵
第5回:5代目は日本酒エンターテイナー 南部美人、新時代の蔵元が世界へ
第6回:リンゴ酵母と大吟醸創る 中尾醸造、竹原が生んだ誠鏡
第7回:レモンワインと日本最古の酒米 中尾醸造、竹原が生んだ誠鏡
第8回:7代目蔵元「3つの理念」で酒造り 蓬莱泉の関谷醸造
第9回:消費者との接点を求めて 蓬莱泉の関谷醸造
第10回:家族が守った手造りの酒 石鎚酒造、杜氏引退で覚悟
第11回:3杯目からうまくなる酒 石鎚酒造、時間かけ作り込む
第12回:誰にも負けぬ酒造りの情熱 「東洋美人」の澄川酒造場
第13回:同士の力で奇跡の復活 澄川酒造場の継承と革新
稲田 宗一郎(いなだ・そういちろう) 千葉県生まれ。本名などを明らかにしていない覆面作家。2021年7月に遊行社から「錯覚の権力者たち-狙われた農協-」を出版した。
最新記事
-

信州そばをインド巨大市場に初出荷、日本縮小で NNA
信州そばの乾麺製造を手がける柄木田(からきだ)製粉(長野市)が、インド向け製品を初出荷した。人口減...
-

ヤクルト、比南部で新工場稼働 能力3割増、全国供給へ体制整う NNA
ヤクルト本社は5月20日、フィリピンの南部ミンダナオ島に建設した第2工場を稼働したと発表した。第1...
-
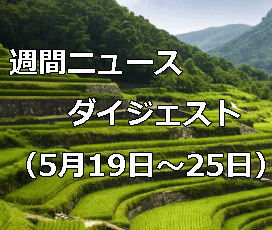
25府県がカメムシ注意報 週間ニュースダイジェスト(5月19日~5月...
▼大手賃上げ、過去最高 5.58%、経団連集計(5月20日) 経団連が発表した2024年春闘の第1...
-

値上がりする果物 日本の果樹産業の未来は 青山浩子 新潟食料農業大学...
物価高とは別に、「近頃、果物が高くなった」と感じる人は多いのではないか。実際、果樹の農家数や生産量...
-

豪産牛肉、日本での販売価格の方が安い? NNAオーストラリア
オーストラリア牛肉協会(ABA)が実施した調査で、日本のスーパーマーケットで販売されるオーストラリ...
-

農林中金、1.2兆円の資本増強へ 25年3月期、5千億円超の赤字で
農林中央金庫の奥和登理事長(写真左)は22日、東京都内で記者会見し、1兆2千億円規模の増資を検討中...
-

GDP年率2.0%減 週間ニュースダイジェスト(5月12日~5月18...
▼40年の脱炭素戦略策定へ 年内めど(5月13日) 政府は2040年の脱炭素や産業政策の方向性を示...
-

食料安保の重要性を指摘 石破元農相が講演 共同通信きさらぎ会で
石破茂元農相・自民党元幹事長は5月17日、都内で開かれた共同通信社主催のきさらぎ会(写真)で「日本...
-

認知障害、高齢3人に1人 60年政府推計 週間ニュースダイジェスト(...
▼テレワーク施設、利用低迷 巨額交付金、検証必要(5月5日) 新型コロナウイルス対策のため国が設け...
-

補助金漬けでは考える力が育たない 赤堀楠雄 材木ライター 連載「グ...
最近、スギやヒノキの人工林を「若返り」と称して皆伐(かいばつ)(一定面積の樹木をすべて伐採すること...

 ツイート
ツイート