つくる
新着ニュース

しなやかな連携で被災者を支援 沼尾波子 東洋大学教授 連載「よんななエコノミ...
2024年元日は能登半島地震に始まった。半島という地形から、災害の起こり方も過去の大規模地震とは異なり、また支援に入ることが難しく、孤立する地域もある。 過酷な被災地の状況に、何か支援をしたい。自治体や日本赤十字社などが始めた義援金の募集には多くの寄付が集まっている。他方で、物資の寄付やボランティ...
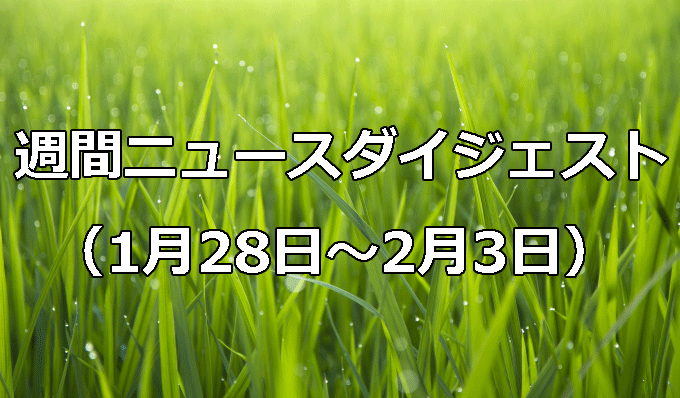
23年農水産輸出2.9%増 週間ニュースダイジェスト(1月28日~2月3日)
▼中小企業被害、数千億円 能登地震、伝統工芸に打撃(1月29日) 能登半島地震による中小企業や小規模事業者への被害が新潟、富山、石川、福井の4県の合計で数千億円規模に上る可能性があることが分かった。揺れや液状化による建物や設備の損壊が多数確認されており、伝統工芸や観光が盛んな地域経済に甚大な打撃が...

現場起点の脱炭素型農業に期待 青山浩子 新潟食料農業大学准教授 連載「グリー...
食料の生産性と持続可能性を両立させるためのイノベーションを通じ、脱炭素社会を実現する。この御旗のもとに、農林水産省が2021年に策定した「みどりの食料システム戦略」。避けて通れない至上命題ではあるが、個々の農業者が積極的にこの話題を口にすることはほぼない。こちらから持ち掛けても「有機農業の面積10...

震災からの復興と離島振興 宮城県女川町 小島愛之助 日本離島センター専務理事 ...
元日に能登半島地震が起きると、宮城県女川町は6日、備蓄していたアルファ米や野菜ジュース、ポリタンク、非常用飲料水袋など生活物資を被災した石川県志賀町に提供し、その3日後には副町長ら職員4人を現地に派遣した。女川町は、東日本大震災の復興支援で志賀町から2015年度に事務員、19年度に保健師の派遣を受...

期待外れの基本法改正 「農業ムラ」から脱皮せよ アグリラボ編集長コラム
(写真は首相官邸ホームページから) 通常国会が1月26日に招集され、岸田文雄首相は30日の施政方針演説で「農政の憲法」とされる食料・農業・農村基本法を改正する決意を示した。ただ、関連法案の整備が貧弱で、具体的な施策が先送りされ、現段階では実効性に乏しい内容になりそうだ。 当初、基本法改正の最大の狙...

ブロッコリーを指定野菜に 週間ニュースダイジェスト(1月21日~1月27日)
▼コメ生産目安、26県が増加 24年産、減少は9県(1月22日) 2024年産の主食用米について、生産量の目安を具体的な数値で示した37道県のうち、26県が23年の収穫量実績に比べ増加を見込んでいることが分かった。9県が減少、北海道と高知県は据え置きだった。 ▼出生数1~11月69万6千人 23年...
