現場起点の脱炭素型農業に期待 青山浩子 新潟食料農業大学准教授 連載「グリーン&ブルー」
2024.02.05

食料の生産性と持続可能性を両立させるためのイノベーションを通じ、脱炭素社会を実現する。この御旗のもとに、農林水産省が2021年に策定した「みどりの食料システム戦略」。避けて通れない至上命題ではあるが、個々の農業者が積極的にこの話題を口にすることはほぼない。こちらから持ち掛けても「有機農業の面積100倍増は無理でしょう」「仮に生産量が増えたとしても、どれほどの消費者が有機農産物を求めるだろうか」という冷めた意見が返ってくる。有機の拡大目標ばかりがクローズアップされたこともあり、出鼻がくじかれたまま今に至っている。(画像は農林水産省「みどりの食料システム戦略」のホームページより)
そんななか、希望を持てる場面に出くわした。昨年12月に新潟県南魚沼地域の若手農家が集まり、「南魚沼で取り組めるみどり戦略とは」についてグループディスカッションが行われた。同県南魚沼地域振興局主催で、私もみどり戦略の概要や考えを話した。
南魚沼といえば、誰もが知る魚沼米の産地だ。同振興局では域内の農業者を対象に、22年に農業と環境保全に関するアンケート調査をしていた。回答したのは300人強。「環境保全への関心」には51%が「あり」と答えている。ただ、有機農業やたい肥利用などの具体策となると、「経費」や「手間」などの理由から取り組みが進んでいないことも分かった。
ディスカッションの冒頭、農業者たちの口はやや重かった。しかし徐々に発言が出てきて、30分もしないうちに、四つに分かれた小グループからそれぞれの意見が出された。そのなかに、エコツーリズムというアイデアが出た。雪深い地域性を生かし、地区内には雪を冷蔵庫代わりにする"雪室"が11カ所もあり、農産物の貯蔵もされている。地の利を生かした施設を見てもらうことで、環境保全型農業を知ってもらうというアイデアだ。別のグループは、米の副産物である、もみ殻やたい肥の活用をさらに促し、資源循環型農業の地域として消費者に知ってもらう必要性を訴えた。
個人的に「なるほど」と思ったアイデアは、「草刈りの回数を減らす」というもの。いったいなんだろうと思われるだろうが、農村部では、田んぼのあぜなどの草刈りを小まめにして、世間的に「自分の田んぼがきれいかどうか」を気にする。そのため、一度刈ったところをもう一度刈るなどということがある。その分、燃料を使い、CO2の排出量が増える。「過剰な草刈りは皆でやめよう」と決め、実際に浸透すれば、環境にもよいし、労力も減るというわけだ。
農業者が自分事として取り組んでこそ、実現可能性も持続可能性も高い。みどり戦略に関連する政策は、有機農業を地域で展開するなどハードルが高いという印象が否めない。土地条件も地域資源を生かした小さなアイデアであっても、採用・支援へとつながる仕組みが導入されれば、生産現場の意識は変わるはずだ。
(Kyodo Weekly・政経週報 2024年1月22日号掲載)
最新記事
-

農水省、備蓄米放出へ転換 1年以内の買い戻し条件 週間ニュースダイジ...
▼コメ2割減で増産指示 食料危機回避へ基本方針(1月28日) 政府は昨年6月に成立した「食料供給困...
-

ハラールラーメン 畑中三応子 食文化研究家 連載「口福の源」
正月に浅草を歩き、至る所にラーメン店が新規開店しているのに驚いた。どこも訪日観光客で賑(にぎ)わっ...
-

「宝島のカボチャ」~孤島の種が関東の土でどうよみがえるか? 菅沼栄一...
群馬県太田市の亀井秀夫さん(72)は年が明けた6日、カボチャの種を、関東地方の約20軒に郵送した。...
-

ブランド化で持続可能な発展 山岳民族のコーヒー農園支援(上) NNA
一般社団法人のアジア自立支援機構(GIAPSA=ジアプサ、茨城県つくば市)は、タイなどで少数民族の...
-
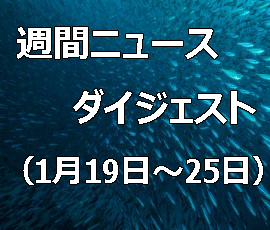
日銀、追加利上げ決定 0.5%に、17年ぶり水準 週間ニュースダイジ...
▼鳥インフル年明け感染加速 4百万羽処分、鶏卵1割高(1月20日) 農林水産省は養鶏場などでの高病...
-
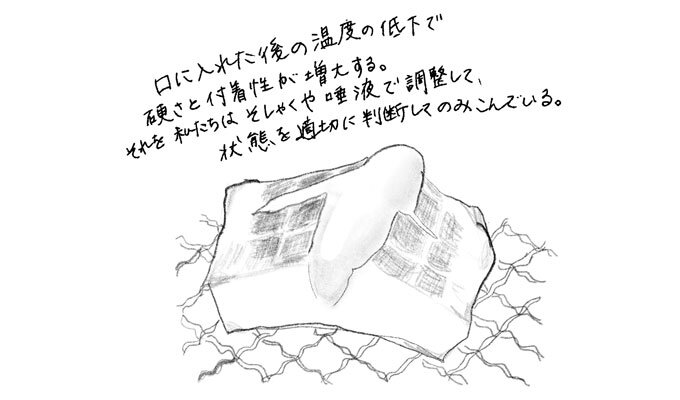
餅とこんにゃくと食品安全 野々村真希 農学博士 連載「口福の源」
この年始に、お雑煮に餅を入れて食べた方は多くおられるだろうか。今更ながらだが、餅を食す際にとにもか...
-
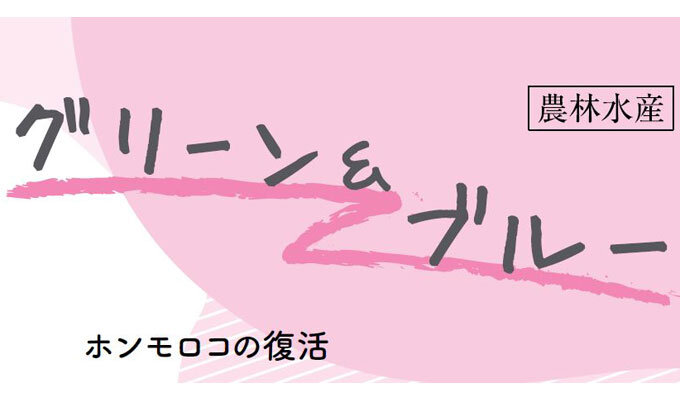
ホンモロコの復活 佐々木ひろこ フードジャーナリスト 連載「グリー...
日本最大の湖、琵琶湖を擁する滋賀には、地域特有の魚食文化が根付いている。 ニゴロブナの塩漬けと米を...
-
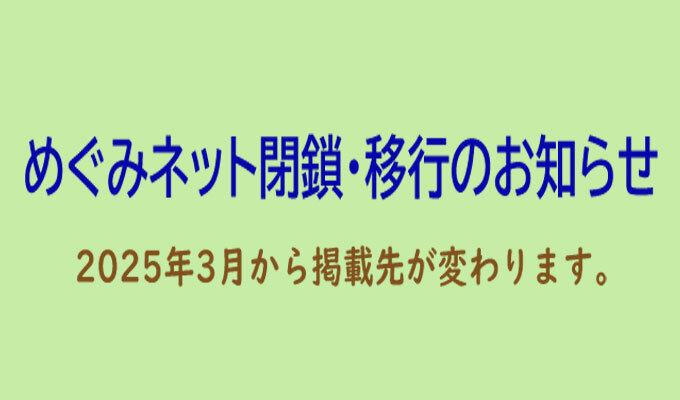
めぐみネット閉鎖・移行のお知らせ
めぐみネットは開設以来、多くの皆さまにご利用いただきましたが、食農分野の情報を他のビジネス情報と融...
-

訪日消費、初の8兆円超 週間ニュースダイジェスト(1月12日~1月1...
▼稲作の新たな栽培方法に大賞 高校生ビジネスコンテスト(1月12日) 全国の高校生らが新規事業のア...
-
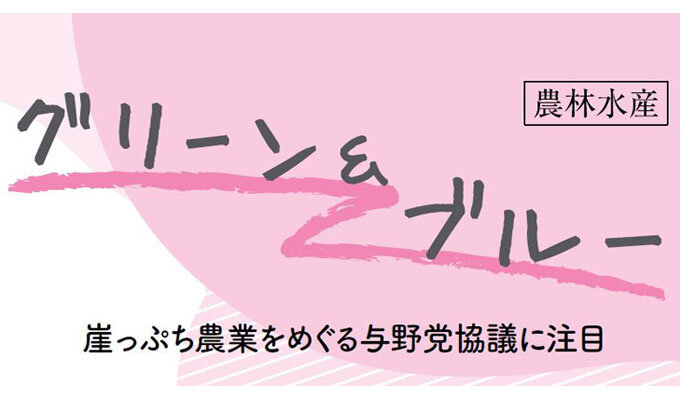
崖っぷち農業をめぐる与野党協議に注目 小視曽四郎 農政ジャーナリスト...
政府の2024年度補正予算案は、28年ぶりに衆院で野党の修正要求をのんで成立する様変わり。少数与党...

 ツイート
ツイート