医療費と労働損失 社会負担1兆円超 田中太郎 共同通信編集委員
2023.09.11

生活習慣の改善などで発症予防が期待できるがんによる日本社会の経済負担は1兆円を超える--。こんな実態が国立がん研究センターがん対策研究所などによる推計で初めて明らかになった。発がんリスクとしては「感染」と「喫煙」が二大要因となることも確認され、その対策が多くのがんを防ぎ、社会の負担も軽減することにつながる。(写真はイメージ)
がんは1981年以降、日本人の死因の首位に座り続けている。罹患した人は2019年で男性約57万人、女性約43万人の計約100万人。死亡者も21年で男性約22万人、女性約16万人の計約38万人に達している。
がんは遺伝的に決まる発症しやすさの「素因」に加え、喫煙や肥満、飲酒などの「生活習慣」、胃がんのヘリコバクター・ピロリ菌や子宮頸がんのヒトパピローマウイルス(HPV)、肝がんの肝炎ウイルスなどの「感染」、放射線や日光、化学物質などの「被ばく」と、さまざまな要因が重なって起きる。いわば、遺伝病でも生活習慣病でも感染症でもあるわけだ。
がん対策研究所は「もしその要因がなかったら、何%のがんが予防可能だったか」を示す「人口寄与割合」(PAF)を算出する「日本人におけるがんの原因の寄与度」研究を続けてきた。PAFは05年に続き、より精度が上がった15年のデータがまとまっており、今回はそれを利用して社会の経済的負担を算出した。研究をとりまとめた同研究所の井上真奈美副所長は「一連のがん予防研究の仕上げに当たる」と位置付けている。
15年のPAFによると、日本人の場合、男性のがんの43%、女性のがんの25%、全体では36%のがんが、予防可能な要因で起きていたことが明らかになった。要因別で見ると、感染が16・6%、喫煙が15・2%と二大要因を占めた。次いで飲酒が6・2%、塩分の高い食事2・4%、運動不足1・3%だった。受動喫煙は0・5%の9位。
次いで、社会の経済的負担では、直接費用としてレセプト(診療報酬明細書)情報などを基に入院、外来、調剤の「がん医療費」を計上。間接費用として、厚生労働省・賃金構造基本統計調査の「期待生涯収入」「一日あたり平均収入」やがん統計などの各種データを基に「死亡による労働損失」と「治療のための(休業による)労働損失」を算出して計上した。
15年に治療を受けた全がん患者の総経済的負担は男性1兆4946億円、女性1兆3651億円の計2兆8597億円。男女間で大きな差はなかった。がん種別で見ると、女性では乳がんが突出して多く、男性では前立腺がん、肺がん、胃がんの順だった。
一方、PAFを使って予防可能ながんの経済的負担を抜き出すと、男性6738億円、女性3502億円の計1兆240億円となった。がん種別の負担では、男女ともに胃がんが最も高く、男性1393億円、女性728億円だった。次いで、男性では肺がんが1276億円、女性では子宮頸がんが640億円と続いた。
さらに、これを直接費用と間接費用に分けて分析すると、女性では乳がんと、特に子宮頸がんで死亡と治療による労働損失が大きくなっていた。これについて、分析に当たった国立国際医療研究センター国際医療協力局の齋藤英子上級研究員は「働き盛りの40代での発症が多いことを反映している」と指摘している。
これら予防可能ながんについて、喫煙、飲酒、感染、過体重、運動不足の五つのリスク要因別に経済的負担を算出した。その結果、最も多かったのは「感染」で4788億円。内訳はピロリ菌による胃がんが2110億円、HPVによる子宮頸がんが640億円、肝炎ウイルスによる肝がんが607億円と推計された。次いで「喫煙」が4340億円。がんや食道がん、胃がんなどさまざまながんの発症に関わっているが、やはり肺がんでの経済的負担が1386億円と最も多くなっていた。
全体で見ると、この二つの要因が突出して負担が大きく、次の「飲酒」は1721億円。「運動不足」は337億円、「過体重」は190億円にとどまった。
多くのがんは生活習慣や環境要因で引き起こされ、それらを適切に予防することで発症を減らすことは以前から言われており、がんを引き起こす要因の研究はこれまでも盛んだった。一方、「がんが社会に与える医療費と労働損失の経済的負担の研究はまだほとんどされておらず、世界的にもこれからの分野」と齋藤さん。
これらのリスク要因のどれが、どの程度寄与しているかは生活習慣や環境などを反映するため、国ごとで微妙に異なる。今回、日本のデータを基にリスク要因が分析できたことで、日本での予防策に優先順位を付け、効果的な対策を立てる際の根拠が得られたことなる。
発がんに関連した「感染」と「喫煙」の対策が効果的なことは明らかで、井上さんは「この二つを効果的に予防することで、多くのがんによる死亡を防げるだけでなく、社会の経済的負担の軽減にもつながる」と強調した。
具体的には、ヘリコバクター・ピロリ菌除菌治療や肝炎ウイルス治療のさらなる徹底に加え、22年から積極的勧奨が再開されたHPVワクチン接種の推進、さらに定期的ながん検診の受診率向上やたばこ対策の強化が重要になる。
(Kyodo Weekly・政経週報 2023年8月28日号掲載)
最新記事
-

日系ラーメンがインド1号店 自社ブランド50店舗へ、サンパーク NN...
外食チェーンを複数手がけるサンパーク(大阪府吹田市)が、インドの南部カルナタカ州ベンガルール(バン...
-
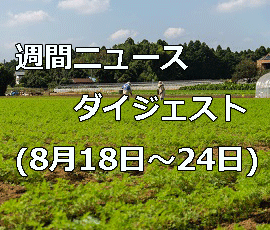
コメ17%高騰、20年ぶり 週間ニュースダイジェスト(8月18日~8...
▼クマ対策、地域の連携強化 環境省、交付金30億円要求(8月19日) 環境省は2025年度予算の概...
-

太平洋クロマグロの漁獲枠拡大で合意 佐々木ひろこ フードジャーナリス...
7月半ば、日本の漁業者がここ数年待ち望んでいた大きなニュースが流れたことをご存じだろうか。マグロや...
-
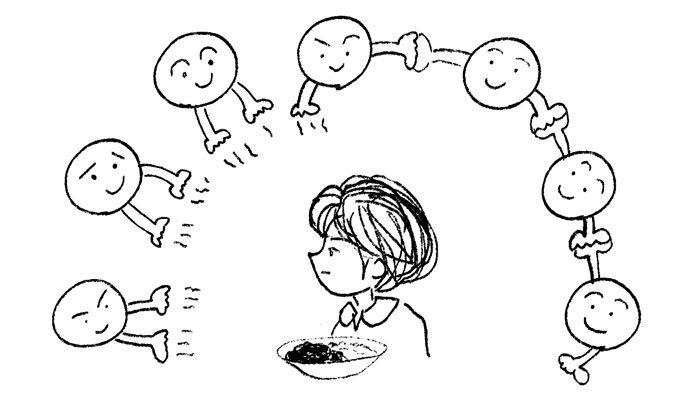
空気を読んだ食事 鬼頭弥生 農学博士 連載「口福の源」
私たちの日々の食行動は、その基盤に自らの意思があるものの、自身の置かれた経済的・物理的状況のほか、...
-

観光ビジネスのプレイヤーの変化 森下晶美 東洋大学国際観光学部教授 ...
コロナ禍以降、観光に関わるビジネスプレイヤーが変化してきている。これまで観光というと、交通事業、宿...
-
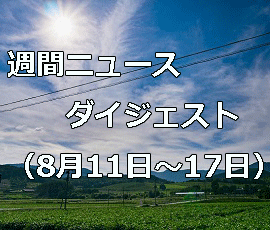
岸田首相退陣へ 自民総裁選不出馬 週間ニュースダイジェスト(8月11...
▼台風5号、東北横断 岩手で記録的雨量、浸水も(8月12日) 台風5号は12日午前8時半ごろ、岩手...
-

目先の値上がりより米自給の存続に目を 小視曽四郎 農政ジャーナリスト...
主食とはいえ、支出額では完全にパンに抜かれ、年間支出額でも2万円を割った米(2022年一世帯食費占...
-

少子化対策に必要なのは安心できる雇用環境 藤波匠 日本総合研究所調査...
少子化が止まりません。厚生労働省が6月に公表した人口動態統計によれば、2023年の日本人の出生数は...
-

地域づくり支える学生マンション 沼尾波子 東洋大学教授 連載「よん...
東京都千代田区神田淡路町にユニークな学生マンション「ワテラススチューデントハウス」がある。ワテラス...
-
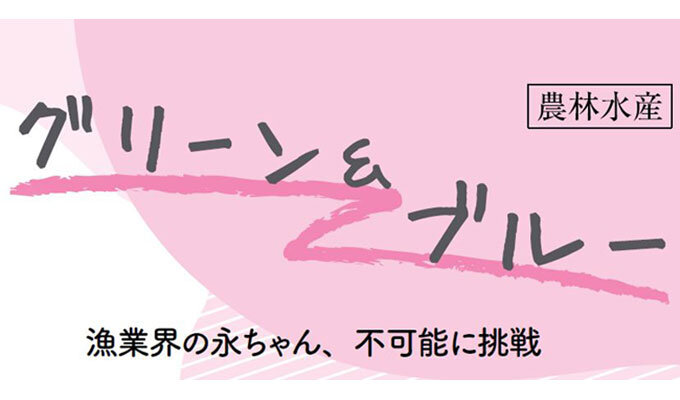
漁業界の永ちゃん、不可能に挑戦 中川めぐみ ウオー代表取締役 連載...
筆者が勝手に「漁業界の矢沢永吉」と称し尊敬する漁師さんが、千葉県にいらっしゃる。スズキの水揚げ日本...

 ツイート
ツイート