指なじみと口触りで変わる味 飲食店の割り箸の歴史 植原綾香 近代食文化研究家
2022.09.26
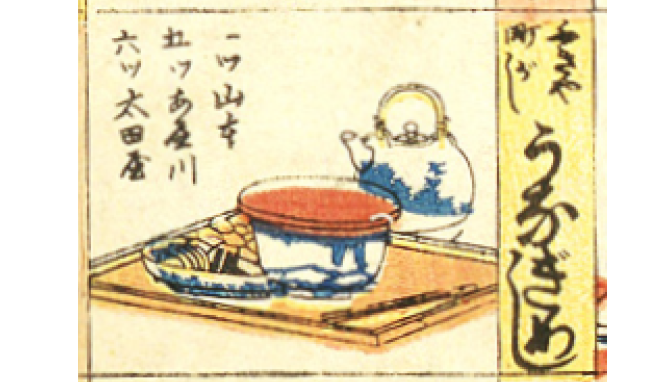
マレーシアに赴任した大学の友人から電話がきた。マレー料理のほかにも中華系の店も多く、日本のたこ焼きや焼き肉もあり、食には不自由しない暮らしだそうだ。
興味深かったのは、飲食店にいくと熱湯のカップがでてくるという話だ。飲みものかと思いきや、それでフォーク、スプーン、箸を洗うのだという。それだけ使いまわしのカトラリーは信用できないということなのだろう。日本でよく見かける割り箸は、マレーシアでは見かけず、使い捨てはフォークばかりだそうだ。
日本の割り箸の歴史を調べていくと、衛生と相即不離にあることがわかる。明治、大正期の箸袋を見ると、屋号の上には「消毒」と大きく文字が書かれたものがみられるのだが、箸が衛生的であるかどうかは、食事をするときの心配事であったらしい。
大正期になると衛生面での取り締まりが厳しくなったそうだが、昭和初期の内職に関する文献には、もともと割り箸や包装紙そのものが消毒済みであったとしても箸袋の内職をする環境自体が悪く衛生的ではないということが問題視されている。
現在広く使用される頭の部分がくっついている割り箸は、もともと「割りかけ箸」や「引裂箸」と呼ばれ、江戸時代の百科事典ともいわれる「守貞謾稿」の「鰻飯」の項には次のように書かれている。「必ず引裂箸を添える。この箸は文政以来ごろより、三都(京、大坂、江戸)とも始め用いる。杉の角箸半ばを割りたり。食するに臨みて裂き分けて用いる。これ再用せず清きを証す」とある。(写真:初代歌川芳艶「江戸飲食名物双六」=嘉永年間(1848~1854年)ごろ、国立国会図書館=から)
つまり割られていないことで、その箸が未使用で清潔であることを示していた。割り箸はもともと今のように使い捨てではなく、幕末には「箸処という商売ができ、引裂箸は高級料亭に売り、その箸の断面を削りなおしてそば屋に売り、またその箸に漆を塗り一膳めし屋に売り、3回儲けた」そうだ。
昭和初期もそうだったのか、三越で食事をした話には「日本一の三越ともあろうものが染めの割箸をつかっているのは困りものだね」という話が出てくる。明治時代に割り箸を出す店はそれだけで高級な料亭とされたそうで、戦前は塗り箸を繰り返し使っていた店が多かった。
放浪記で知られる林芙美子の作品には「飲食店にはいって、ふっと、箸立ての汚い箸の束を見ると、私には卑しいものしかないのを感じる。人の舌に触れた、はげちょろけの箸を二本抜いて、それで丼飯を食べる。まるで犬のような姿だ」とか「ここのおかみさんはケチなので割り箸は使わずに、洗って何時までも使える青竹色に塗った箸をつかっていました」などと使いまわしの塗り箸が貧しい描写としてでてくる。
ところで、外食先の割り箸でも杉の利休箸や柳の両口箸であると、よくある先の四角い元祿箸よりも口あたりがよくおいしいような感じがする。言ってみればたった2本の棒なのに、指なじみと口触りの良さで味が変わってくるのは不思議なものだ。どんな箸で食事をするのかは、意外と重要な要素なのかもしれない。
最新記事
-

明治大正期に大衆化 郷愁感じる「縄のれん」 植原綾香 近代食文化研...
外の空気が冷たくなってくると、赤ちょうちんの情景が心に浮かび、手狭で大衆的な居...
-

何個も食べられる甘さ加減 あばあちゃんのおはぎ 眉村孝 作家
宮崎駿監督のアニメ「となりのトトロ」で、サツキ・メイ姉妹の一家が田舎へ引っ越し...
-

おおらかに味わうシメの1杯 「元祖長浜屋」のラーメン 小川祥平 登...
古里の福岡を離れた学生時代、帰省の際は旧友とたびたび街へ繰り出した。深夜まで痛...
-

指なじみと口触りで変わる味 飲食店の割り箸の歴史 植原綾香 近代食...
マレーシアに赴任した大学の友人から電話がきた。マレー料理のほかにも中華系の店も...
-

街ごと楽しむ餃子 宇都宮で「後は何もいらない」 眉村孝 作家
6月下旬の週末の夕方。宇都宮市に単身赴任中の先輩Zさんと合流すると早速、JR宇...
-

東京にある「古里の味」 73年から豚骨ラーメン 小川祥平 登山専門...
京都小平市の西武鉄道「小川駅」から歩く。近づくにつれて漂ってくるにおいに「あれ...
-

あめ色に煮込んだカキ 宮城・浦戸諸島の味 小島愛之助 日本離島セン...
日本三景の一つである宮城県・松島湾に浮かぶ浦戸諸島、250を超える島々で形成さ...
-

特別なキーマカレー 利根川「最初の1滴」食べた 眉村孝 作家
「利根川の最初の1滴をくみ、みんなで朝のコーヒータイムを楽しみませんか」。こん...
-

戦火のがれきからよみがえった酒 沖縄、百年古酒の誓い 上野敏彦 記...
県民の4人に1人が犠牲になった沖縄戦。今年の5月15日は沖縄が日本に復帰して5...
-
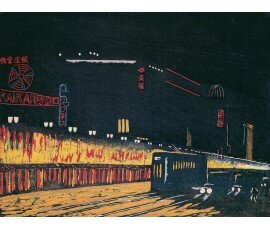
カフェー情緒が濃厚だったころ 版画「春の銀座夜景」に思う 植原綾香...
仕事を終えて外にでると、蒸した空気に潮の香りが混ざっている。夏が来たと思う瞬間...

 ツイート
ツイート