戦火のがれきからよみがえった酒 沖縄、百年古酒の誓い 上野敏彦 記録作家
2022.07.25

県民の4人に1人が犠牲になった沖縄戦。今年の5月15日は沖縄が日本に復帰して50年の節目ということで、メディアもさまざまな報道を繰り広げた。しかし、沖縄には全国の米軍施設の7割が今も集中するだけに、県民の間では本土の踏み台とされた戦時中の構図と何ら変わらないとの反発も強かった。
6月23日の慰霊の日は沖縄戦の組織的戦闘が終結した日で、県民は戦争で亡くなった人々の霊を慰めるが、その場で欠かせないものは600年の歴史を誇る琉球民族の酒・泡盛だろう。
キュッとやると、口の中に広がる甘くて辛い、独特な風味が忘れられない。沖縄へ40年も通っているのは、泡盛を現地でのみたい気持ちが強いからだ。
あの大戦では米軍の猛爆撃にあって陸軍第32軍の地下司令部があった首里の町は壊滅的な打撃をこうむった。泡盛の酒蔵はガレキの場と化し、200~300年物の古酒(クース)の入ったかめもすべてが失われた。
そんな焼け跡に1945年の暮れ、1人の男が米軍の収容所から解放されて帰ってきた。咲元酒造の2代目佐久本政良で、焼け残ったニクブク(むしろ)に泡盛の製造に必要な黒こうじ菌が生き残っているのを発見して、ほかの醸造所にも分け与え伝統の泡盛は奇跡の復活を果たしたのである。(上の写真:こうじを造り込む咲元酒造の4代目佐久本啓=2015年、牧野俊樹撮影)
ところが米国統治下の沖縄では輸入物の高級ウイスキーが安く出回っているため泡盛は顧みられず、のみ屋の店主も「こんな貧乏酒を置いとくのは恥ずかしい」と言って一升瓶をカウンターの下に隠すのが酒場の風景だったという。
専門酒場と業界紙
今から半世紀前の1972年8月15日。那覇市の栄町市場の脇に泡盛専門の居酒屋「うりずん」を開いたのが土屋実幸、30歳だった。当時57あった全酒蔵の泡盛を置いた酒場はなく、沖縄本島のみならず離島の酒も旅に出た友人に買い集めてもらい、すべての品数をそろえた。
土屋が理想とする泡盛は琉球王国最後の末裔、尚順が愛したクースで、「時間をかけて熟成させれば泡盛は世界一の酒になる」と夢を持ってのことだった。
当初は閑古鳥が鳴いていたうりずんも開店して2、3年たつと地元の泡盛好きでにぎわうようになり、椎名誠ら本土の著名人もやって来るようになると観光客の間でも評判になった。
1983年に泡盛は洋酒の消費量をしのぐことになり、2001年にはNHKの朝ドラマ「ちゅらさん」で泡盛は全国的に注目され、2004年には生産がピークに達した。
その後、生産は減っているが、高品質の多彩な酒が出回るようになり、泡盛ルネサンスと呼ばれるような状況も見せている。
泡盛をここまで盛り立てたのは1969年に「醸界飲料新聞」を創刊した仲村征幸によるところが大きかった。仲村は泡盛の蔵元が集まってウイスキーをのみながら「ウチの酒が売れない」とぼやくのを見ると、「泡盛はメーカーだけのものではなく、県民共通の財産であることを忘れるな」と一喝するのだった。

(クースのご意見番、仲村征幸(右)と土屋実幸=2014年)
仲村は泡盛同好会を全国各地に発足させて、泡盛の魅力を底辺から広げる努力をすると同時に、1997年に土屋と百年古酒を造る会を発足させた。
ウクライナ侵略と沖縄戦
その土屋実幸が2014年に100年寝かせたクースを利き酒する機会があり、「えも言われぬ甘さと、丸い香りに驚いた」と感想を語っていた。
現在泡盛の古酒は「時雨(しぐれ)」を造る識名酒造に150年と130年物が保管してあるほか、沖縄に100年を超える酒はない。
土屋が味わった100年物は1904年に後に講談社を創立する野間清司が県立沖縄中学に教諭として赴任していたときの弟子から感謝の品として贈られたものだった。
野間家の倉庫に長い間保管され、東京大空襲の戦火にも耐えながら眠り続け、創業100年の社員懇親会で初めてお披露目された門外不出の酒だった。
土屋は「あの戦争さえなければわれわれは何百年も熟成させた大古酒を味わうことができたのではないか。将来二度と戦争を起こさない平和な世の中をつくり、沖縄全体をクースの島にしたい」と感想を語っていた。
「泡盛のご意見番」「クースの番人」などと呼ばれた仲村征幸と土屋実幸は2014年に相次いで天上の人となっていった。83歳、73歳だった。
この2月、突然勃発したロシアのプーチン大統領によるウクライナへの軍事侵略。学校や病院が爆撃され、多くの市民が犠牲になった映像に全世界は衝撃を受けた。これこそが沖縄戦の再来というものだ。
土屋実幸と仲村征幸が常々口にしていた百年古酒とは、こうした戦争の対義語になる平和を意味するものなのである。戦火のガレキからよみがえった酒を皆で大事に育てることにより地上から争いごとを追放していきたい。というのが沖縄の人々の願いであり、琉球泡盛の真髄にあることを心に刻んでいきたいと思うのである。(敬称略)
琉球泡盛の歴史と現状を7月15日発行の「沖縄戦と琉球泡盛 百年古酒の誓い」(明石書店)で紹介しました。(うえの・としひこ=記録作家、元共同通信編集委員)
(Kyodo Weekly・政経週報 2022年7月11日号掲載)
最新記事
-

明治大正期に大衆化 郷愁感じる「縄のれん」 植原綾香 近代食文化研...
外の空気が冷たくなってくると、赤ちょうちんの情景が心に浮かび、手狭で大衆的な居...
-

何個も食べられる甘さ加減 あばあちゃんのおはぎ 眉村孝 作家
宮崎駿監督のアニメ「となりのトトロ」で、サツキ・メイ姉妹の一家が田舎へ引っ越し...
-

おおらかに味わうシメの1杯 「元祖長浜屋」のラーメン 小川祥平 登...
古里の福岡を離れた学生時代、帰省の際は旧友とたびたび街へ繰り出した。深夜まで痛...
-

指なじみと口触りで変わる味 飲食店の割り箸の歴史 植原綾香 近代食...
マレーシアに赴任した大学の友人から電話がきた。マレー料理のほかにも中華系の店も...
-

街ごと楽しむ餃子 宇都宮で「後は何もいらない」 眉村孝 作家
6月下旬の週末の夕方。宇都宮市に単身赴任中の先輩Zさんと合流すると早速、JR宇...
-

東京にある「古里の味」 73年から豚骨ラーメン 小川祥平 登山専門...
京都小平市の西武鉄道「小川駅」から歩く。近づくにつれて漂ってくるにおいに「あれ...
-

あめ色に煮込んだカキ 宮城・浦戸諸島の味 小島愛之助 日本離島セン...
日本三景の一つである宮城県・松島湾に浮かぶ浦戸諸島、250を超える島々で形成さ...
-

特別なキーマカレー 利根川「最初の1滴」食べた 眉村孝 作家
「利根川の最初の1滴をくみ、みんなで朝のコーヒータイムを楽しみませんか」。こん...
-

戦火のがれきからよみがえった酒 沖縄、百年古酒の誓い 上野敏彦 記...
県民の4人に1人が犠牲になった沖縄戦。今年の5月15日は沖縄が日本に復帰して5...
-
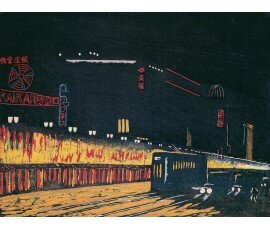
カフェー情緒が濃厚だったころ 版画「春の銀座夜景」に思う 植原綾香...
仕事を終えて外にでると、蒸した空気に潮の香りが混ざっている。夏が来たと思う瞬間...

 ツイート
ツイート