ボルシチはおいしかったが... ウクライナでコメなし50日 水谷竹秀 ノンフィクションライター
2022.06.20

「郷に入っては郷に従え」ということわざがある。訪れた土地の文化や風習に従うべき、という意味だ。取材で海外に出る時、私は現地の料理を食べるのを鉄則にしてきた。だから日本料理店には目もくれない。
戦地のウクライナで取材をするため、日本をたった3月下旬時点でもそう決めていた。ポーランドを経由し、陸路で国境を越えてウクライナに入ったのは3月末。西部の都市リビウに滞在した数日間は、ウクライナ人たちが案内してくれたレストランへ行き、紅色のスープ「ボルシチ」などを堪能した。(写真:おいしかったリビウでのボルシチ=3月、筆者撮影)
そもそもであるが、ボルシチはウクライナが発祥であることをご存じだろうか。ロシアだと思われがちだが、実はウクライナなのだ。ジャガイモやタマネギなどを煮込み、ビーツで紅色に仕上げる伝統的なスープの味は、酸味がある。
リビウでは一度だけ、アジア系の料理店に入って焼き飯を食べた。鶏肉のほか、ヤングコーンとズッキーニが入っていて、味はやや甘め。日本人がイメージする焼き飯とはかなり異なった。
4月上旬から1カ月強滞在した首都キーウでの食事はもっぱら、宿泊先のホテルで取った。というのもキーウは夜間外出禁止令が継続中で、営業している飲食店も午後8時には閉店する。取材で夕方以降にホテルに戻ってくると、外食できる店がないため、食事はホテルのビュッフェに限られてしまう。
ホテルは大統領府から約500㍍離れたキーウ中心部に位置し、宿泊客の大半は欧米の報道関係者。1泊75ユーロ(約1万円)で、ビュッフェの料金は400フリブニャ(約1700円)と決して安くはない。メニューは肉料理やパスタ、サラダ、ボルシチなどが中心で、コメはほとんど出ない。泊まり始めのころはそれでも良かったが、やがてコメのない生活に音を上げ始めた。
周辺には日本料理店もない。ウクライナに在留する日本人は戦争前でも約200人と、他国に比べて圧倒的に少ないためだ。代わりに中華を探し回ったが、いわゆるラーメン一杯を食べられるような日本風の「町中華」はなかった。それでも徒歩で30分かけて中華風の店に入り、焼き飯とスープ麺を注文。焼き飯の甘さに、あっさり裏切られた。
食事が満たされない日々に限界がきたころ、思い切ってモダンなすし屋に入った。すし屋といっても、カリフォルニア巻きのような巻きずしが主流だ。そこでみそ汁を注文。具材はワカメとシメジ、豆腐に加え、なぜかえんどう豆が混入されていた。味はやはり甘め。みそ独特の塩気が感じられなかった。こんなことなら、パックのみそ汁でも持ってくれば良かった。
こうしてアジア料理に「飢え」た50日間を終え、日本に帰国後、最初に飲んだみそ汁の味には震えた。
(Kyodo Weekly・政経週報 2022年6月6日号掲載)
最新記事
-

明治大正期に大衆化 郷愁感じる「縄のれん」 植原綾香 近代食文化研...
外の空気が冷たくなってくると、赤ちょうちんの情景が心に浮かび、手狭で大衆的な居...
-

何個も食べられる甘さ加減 あばあちゃんのおはぎ 眉村孝 作家
宮崎駿監督のアニメ「となりのトトロ」で、サツキ・メイ姉妹の一家が田舎へ引っ越し...
-

おおらかに味わうシメの1杯 「元祖長浜屋」のラーメン 小川祥平 登...
古里の福岡を離れた学生時代、帰省の際は旧友とたびたび街へ繰り出した。深夜まで痛...
-

指なじみと口触りで変わる味 飲食店の割り箸の歴史 植原綾香 近代食...
マレーシアに赴任した大学の友人から電話がきた。マレー料理のほかにも中華系の店も...
-

街ごと楽しむ餃子 宇都宮で「後は何もいらない」 眉村孝 作家
6月下旬の週末の夕方。宇都宮市に単身赴任中の先輩Zさんと合流すると早速、JR宇...
-

東京にある「古里の味」 73年から豚骨ラーメン 小川祥平 登山専門...
京都小平市の西武鉄道「小川駅」から歩く。近づくにつれて漂ってくるにおいに「あれ...
-

あめ色に煮込んだカキ 宮城・浦戸諸島の味 小島愛之助 日本離島セン...
日本三景の一つである宮城県・松島湾に浮かぶ浦戸諸島、250を超える島々で形成さ...
-

特別なキーマカレー 利根川「最初の1滴」食べた 眉村孝 作家
「利根川の最初の1滴をくみ、みんなで朝のコーヒータイムを楽しみませんか」。こん...
-

戦火のがれきからよみがえった酒 沖縄、百年古酒の誓い 上野敏彦 記...
県民の4人に1人が犠牲になった沖縄戦。今年の5月15日は沖縄が日本に復帰して5...
-
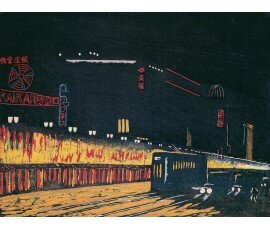
カフェー情緒が濃厚だったころ 版画「春の銀座夜景」に思う 植原綾香...
仕事を終えて外にでると、蒸した空気に潮の香りが混ざっている。夏が来たと思う瞬間...

 ツイート
ツイート