「動物福祉」先行する欧州 デンマーク、母子豚放牧の現場 共同通信アグリラボ所長 石井勇人
2022.09.26

家畜をできるだけ恐怖や苦痛などストレスが少ない環境で育てる「動物福祉(アニマルウェルフェア)」の考え方が国際的に広がり、農林水産省も動物福祉の指針の策定を進めている。養豚を例に、動物福祉の分野で先行するデンマークの事情を報告する。(写真:動物福祉を重視して母子ともに放牧するデンマークの養豚場=ユトランド半島中央部)
「戸建て」で暮らす母子豚
ユトランド半島中央部の丘陵に、インゲ・ボルグさんとブライアン・ホルムさん夫妻の広大な農場がある。250㌶のうち85㌶は、4㍍間隔で植えられた並木で3区画に仕切られた牧草地だ。母豚600頭を飼育し、年間1万2000頭を食肉用に出荷している。
母豚はそれぞれ専用の豚舎(写真左端:2022年7月1日撮影)を与えられ、この「自宅」で分娩し授乳もする。母豚は鼻先で土をほじくり返し、子豚は勝手に走り回り、空腹を覚えれば母豚のところに戻ってくる。
「(私の農場の)食肉を購入する消費者は、その豚がより幸せに暮らしていると考えているからだ」とボルグさんは、消費者の期待を裏切らないために、放牧によって自然な生態を維持するように努めている。政府の規制というよりは、消費者の意識の高さが動物福祉の原動力だ。元気に走り回る子豚を眺めながら「健康に育つだけでなく、肥料(豚の糞尿)も満遍なく散布される」とボルグさんはほほ笑んだ。
飼育頭数に応じて麦などの作付けが義務付けられているため、養豚用の放牧地は麦などの畑に囲まれており、2年ごとに放牧地と畑を入れ替える。さらにセイヨウカリンやカシスが植林され、区画用の並木も含め合計20㌶が林地となっている。(写真:22年7月1日撮影)
ボルグさんは「豚は樹木が大好きで、環境にも良い」と説明する。剪定した樹木はチップにして農場に散布する。大気中の二酸化炭素を固定化できるというわけだ。
ストレスの少ない環境で育てられた豚の肉は、農業協同組合系の食肉加工販売会社を通じて出荷している。意外にも出荷先の95%は、デンマークにとって豚肉の国際市場で最強のライバルである米国である。その理由についてボルグさんは「米国でも抗生物質を含まない食肉の需要はとても強いが、供給できる農場が少ない。最も高く売れる市場に売る」と経営者の顔付きで説明してくれた。
放牧の弱点
ボルグさんが最も警戒しているのは伝染病だ。イノシシなどの野生動物がウイルスを媒介するため、放牧の弱点となっている。豚熱への対策を問われると「健康に育った豚は病気に強いけれど、祈るしかない」という。実際に苦い経験もある。かつて放し飼いで9000羽の採卵用養鶏も手がけていたが、鳥インフルエンザの流行で全面撤退を余儀なくされた。
防疫の観点から、専門家の間では放牧に対する評価が割れており、農林水産省が進めている指針作りが難航している理由の一つでもある。「家畜を病気から守り健康に育てることが動物福祉」(畜産技術協会)と考えるからだ。
衛生管理を徹底するため、養鶏の「ウインドレス」と呼ばれる密閉鶏舎と同様の飼育方法が米国などで研究・開発されており、日本でも一部で試験的に導入されている。
(栃木県畜産酪農研究センターの窓がない密閉豚舎。周辺は防疫対策で石灰が散布され、内部は非公開=22年4月18日撮影)
筆者が以前に訪れた米国のコロラド州立大学の実験施設(写真:11年2月15日撮影)では、肥育段階まで屋外に出さず、成長に必要な周波数の光だけを照射し、さまざまな予防薬を与えていた。
コロラド州立大の担当者は「消費者は誤解している。放牧はのどかな印象を与えるかも知れないが、情緒と科学は区別する必要がある。幼豚は感染症だけでなく野犬や野鳥に襲われ、母豚の下敷きになって圧死するなどさまざまな危険にさらされる。投薬で健康を維持するのは当然のことだ。人間でも薬やワクチンで病気を予防するではないか」と放牧の矛盾点を指摘し、病気から守ることこそ動物福祉であると強調した。

(コロラド州立大附属農場の密閉豚舎の内部=11年2月15日撮影)
隔離型の密閉豚舎は安定した品質で計画的に供給できるため、豚の価値を高めることができる。家畜はペットと異なり、人間の経済活動にとって有用であることが前提になる。
ボルグさんの農場の子豚も、母豚や兄弟豚との幸せな生活は授乳期だけで終わり、成長期に入れば月齢ごとに集団で隔離して肥育し、最終的には食肉処理される。
母子放牧は偽善なのか。密閉豚舎とどちらが幸せなのか。豚に聞いてみないと分からない。ただ豚の気持ちになって深く考えてみると、幼少期だけにせよ広々としたところを走り回り家族と暮らした記憶は、その後の生育にも大きな影響を与えると感じる。(文・写真=共同通信アグリラボ所長 石井勇人)
最新記事
-
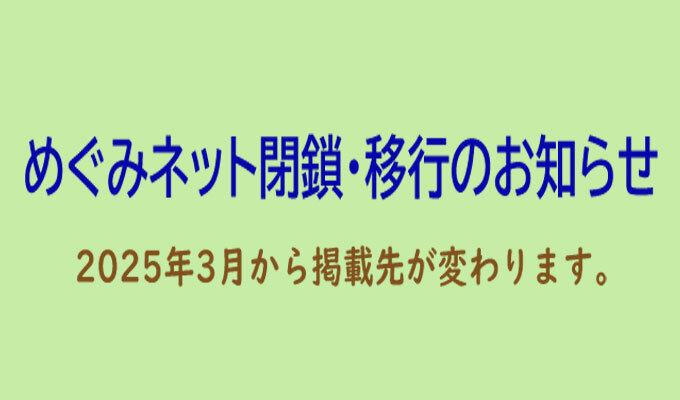
めぐみネット閉鎖・移行のお知らせ
めぐみネットは開設以来、多くの皆さまにご利用いただきましたが、食農分野の情報を...
-

訪日消費、初の8兆円超 週間ニュースダイジェスト(1月12日~1月1...
▼稲作の新たな栽培方法に大賞 高校生ビジネスコンテスト(1月12日) 全国の...
-

地方創生2.0に期待すること 藤波匠 日本総合研究所調査部上席主任研...
9月の自民党総裁選で石破茂新首相が選出されて以来、地方創生が再び政治課題の俎上...
-
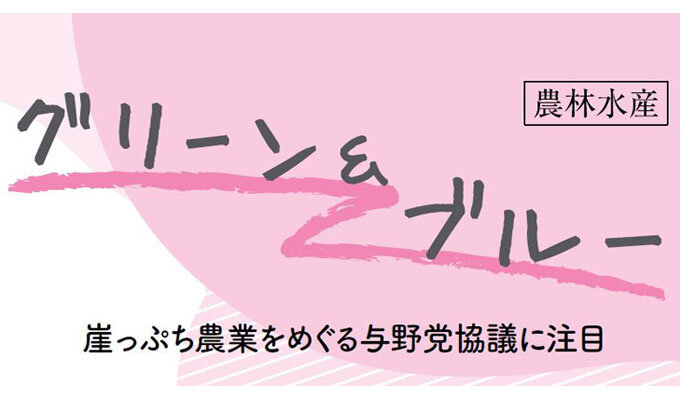
崖っぷち農業をめぐる与野党協議に注目 小視曽四郎 農政ジャーナリスト...
政府の2024年度補正予算案は、28年ぶりに衆院で野党の修正要求をのんで成立す...
-

食品輸出促進で稼ぐ力強化 週間ニュースダイジェスト(1月5日~1月1...
▼大間マグロに2億円 2番目高値、豊洲で初競り(1月5日) 東京都江東区の豊...
-

予算膨張115兆円超え 25年度、歳出・税収最大 週間ニュースダイジ...
▼農業総産出額2年連続増 23年、コメや鶏卵価格上昇(12月24日) 農林水...
-

生きる力学べる港町 中川めぐみ ウオー代表取締役 連載「グリーン&...
「食を通して『生きる力』を学ぶ交流学習」。福井県小浜市の阿納(あの)という総人...
-

飲み会対策教えます 安武郁子 食育実践ジャーナリスト 連載「口福の...
年末年始は飲み会やパーティーが増える季節ですね。楽しい時間を過ごす一方で、歯や...
-

ふるさと納税の功罪 沼尾波子 東洋大学教授 連載「よんななエコノミ...
年末を迎え、ふるさと納税の返礼品をめぐる「商戦」が活発化している。ふるさと納税...
-

米ナスに懸ける20年間の生産者の努力 青山浩子 新潟食料農業大学准教...
あるレシピ検索サイトで、検索用語の首位が「簡単」から「ナス」に変わったというニ...

 ツイート
ツイート