欧州で進む「草」への転換 米州産大豆からの脱却目指す 共同通信アグリラボ所長 石井勇人
2022.08.12

農業生産と地球環境との調和を目指す潮流が強まる中、欧州では畜産業のあり方が見直されるだけでなく、家畜の飼料の供給源として米州産大豆への依存から脱却する動きが強まっている。肉や大豆に代わるタンパク質を確保する上で、切り札となるのは意外にも「草」だ。(写真:タンパク質の供給源として草に着目するデンマークの農村部=ユトランド半島中央部)
標的になる畜産業
畜産業は多くの穀物と水を必要とし、穀物需給を逼迫させるなどの問題が指摘されてきた。環境面でも排泄物の処理が課題で、特に牛はメタンガスを大量に排出するため、地球温暖化への対応を迫られている。
主要国のトップリーダーが集まり、ビジネス分野の国際潮流に大きな影響を与える世界経済フォーラム(WEF、ダボス会議)が、2018年に白書「食肉の未来」を公表したことで、変革へ向けた機運が一気に高まった。白書は「畜産業は温室効果ガスを大量に排出しており、家畜の飼料を栽培するための農地は、森林破壊の最大の要因で生物多様性の損失を招いている」と厳しく指弾し、「従来のタンパク質の供給システムは将来の選択肢ではない」と断じた。
もちろん、畜産業界からは反論もあるが、既存の畜産業の形態が持続可能ではないという認識が広がり、既に日本を含め、大豆など植物性タンパク質からつくる代替肉の市場は拡大が始まっている。今後は細胞から増殖する培養肉の実用化も進みそうだ。
タンパク質の自給戦略
こうした国際潮流を受けて、スイス、ドイツ、オランダなどでは放牧を再評価する動きが強まっている。中でも強い危機感を持ち、敏感に反応しているのがデンマークだ。酪農と養豚が同国の基幹産業であるだけでなく、地球環境に対する市民の意識が極めて高いからだ。畜産業を「農業分野のアキレス腱」と位置付け、農業団体、政府、企業、研究機関などが連携し、持続可能で革新的な生産への転換を目指している。
その目標の一つが、18年から始まったタンパク質の完全自給戦略だ。「ソイ・フリー」(大豆不使用)を掲げ、年間170万㌧の大豆の輸入をゼロにする。大豆を使わない理由は、環境破壊と遺伝子組み換え作物に対する懸念である。
デンマークの農業専門誌記者は「南米産の輸入大豆のうち、森林破壊と無関係だと証明できる大豆は20%しかない。また北米産大豆のうち、遺伝子組み換えではない大豆は供給量が限られ価格が高い」と説明する。
(高級芝生の種子最大手のDLFはタンパク質供給源として草に着目、品種改良に取り組む=同社の試験農場、2022年6月26日撮影)
大豆から草へ
大豆以外に有力な植物性タンパク質はあるのか。デンマークの牧草農家で構成する協同組合の傘下で世界7位の種子会社DLF(本社ロスキレ)のスティグ・オーデルシェデ広報部長は「鍵を握るのは草だ」と断言する。
草は農地の面積当たりのバイオマス(生物資源)の蓄積量が小麦、トウモロコシ、大豆などよりも多い上、越年して成長する多年生植物のため、毎年耕して種子をまき、刈り取るという一連の農作業が不要で、投入する労働力、肥料、燃料を大きく減らせ、環境負荷が小さい。栽培地域に棲息する生物多様性も豊かだ。
関連記事:越冬する新しい稲作 小規模栽培向け、普及始まる
(イネ科の芝、交雑を防ぐためカバーを掛けて品種を改良する)
同社はデンマークの農協系有力企業と共同出資で、「バイオリファイン・デンマーク」(本社ニブロベイ)を設立、草からタンパク質を取り出す工場を昨年稼働した。ユトランド半島西岸に近い同社の工場には、周辺の3000㌶の農場から有機栽培のクローバーやアルファルファが集まる。フル稼働すれば年間7000㌧のタンパク質を生産できるという。
草からタンパク質を取り除いた絞りかすからは繊維を取り出し、布に加工する。残りの液体をバイオガスの燃料にするなど副産物の利用も研究中で、「まったく無駄がない」(バン・フンデボル最高経営責任者)と、草の需要拡大に強い期待を示している。
同社に先駆け、20年9月にユトランド半島北部のアウスムガードでも、同国初の草からタンパク質を抽出する工場が稼働している。小規模な農協が合併した「ベスティランズ・アンデル」(組合員約4000人)が主導し、農業普及機関、研究・開発機関などと連携、クローバなどの草を原料に52%のタンパク質を含む飼料1500㌧を生産している。
同組合のステーン・ビッチュ最高経営責任者は、新型コロナの感染拡大やウクライナ戦争で物流が不安定になっていることを踏まえ、「タンパク質の供給源を分散化する必要があり草の比率を高めたい」と語る。
 (草の潜在力を力説するスティグ・オーデルシェデDLF広報部長)
(草の潜在力を力説するスティグ・オーデルシェデDLF広報部長)
エンドウとソラマメ
タンパク質の自給戦略のうち、飼料の鍵が草なのに対し、食用はファバ(ソラマメの一種=写真左)やイエローピー(エンドウ豆の一種=右)が注目されている。
ユトランド半島中央部の東岸にある「オーガニック・プラント・プロティン」(本社ヘデンステッド=写真)は、大豆以外の植物性タンパク質を利用した代替肉を「プラント・メイト」というブランドで商品化した。
経営者のフィー・グラウゴーとウルリッヒ・ケルン・ハンセン夫妻は「家畜の数が多過ぎて地球環境を破壊している」と、経営していた有機食肉会社を売却してその資金で19年に新会社を設立、翌年に植物由来のタンパク工場を稼働した。現在は1日当たり40万食を供給、76%はフランスなど欧州を中心に輸出し、創業わずか3年で代用肉の大手の一角となった。
「食肉の転換を円滑に進めるためには、栄養でも味覚でも慣れている形で提供する方がよい」(ハンセンさん)と、ハンバーガー、ピザ、パスタなどの形で提供されることを想定した代替肉を販売。素材はすべて有機・無添加だ。

(調理後の代替肉は味覚も食感も従来の肉とほとんど区別できない)
工場がフル稼働すると、エンドウ豆6700㌶とソラマメ1300㌶の作付けが必要になる。周辺の農家の協力が不可欠だが、「植物由来の有機食品に対する需要は、若者を中心にとても強く、国連や欧州連合の政策目標に沿っている」(ハンセンさん=下の写真)と経営に自信満々だ。

日本への示唆
日本でもこの数年、代替肉の市場は拡大しているが、原料はほとんどが米州産の大豆だ。輸入大豆への依存からの脱却や、タンパク質という栄養素に着目した自給率目標の面で、デンマークの戦略とは大きく異なる。
関連記事:「菜食主義の肉屋」とは プラントベース食品が多様に
関連記事:栄養素で考えたい食料自給率 タンパク質に着目する北欧
ブラジルなどは「大豆の増産と森林破壊は無関係」と反論、「国際的な食料供給の責任を果たしている」と主張する。デンマークの「大豆離れ」の理由は、持続可能な開発目標(SDGs)に沿うという理念だけではない。
19年6月28日に大枠合意した欧州連合(EU)と南米の関税同盟である南部共同市場(メルコスル)の自由貿易協定(FTA)が発効すれば、南米産大豆の輸入が増え、飼料の外国依存が強まるという現実的な警戒がある。
欧州の動きがそのまま日本に当てはまるわけではないが、生産から消費までの供給網の統合が進む中、消費者側から大豆の利用と環境破壊を結びつける意識が高まれば、いずれ日本の畜産・食肉産業も対応を迫られるだろう。(文・写真=共同通信アグリラボ所長 石井勇人)
最新記事
-
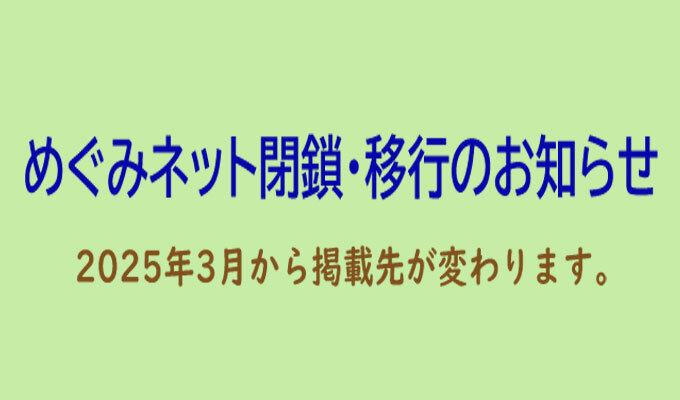
めぐみネット閉鎖・移行のお知らせ
めぐみネットは開設以来、多くの皆さまにご利用いただきましたが、食農分野の情報を...
-

訪日消費、初の8兆円超 週間ニュースダイジェスト(1月12日~1月1...
▼稲作の新たな栽培方法に大賞 高校生ビジネスコンテスト(1月12日) 全国の...
-

豪でも鳥インフル猛威 供給不足で卵の購入制限続く
鳥インフルエンザの感染拡大などによる鶏卵不足から、オーストラリアではスーパーマ...
-

日本食店数3%増で過去最大 タイ 成長は鈍化、総合和食が1位に NN...
日本貿易振興機構(ジェトロ)バンコク事務所は1月8日、タイで営業する日本食レス...
-

食品輸出促進で稼ぐ力強化 週間ニュースダイジェスト(1月5日~1月1...
▼大間マグロに2億円 2番目高値、豊洲で初競り(1月5日) 東京都江東区の豊...
-

コメ交渉の実像伝えず 期待外れの外交文書 アグリラボ編集長コラム
新年を迎えてもコメ相場の高騰が続き、ついに関税を払ってでも米国産を輸入する業者...
-

予算膨張115兆円超え 25年度、歳出・税収最大 週間ニュースダイジ...
▼農業総産出額2年連続増 23年、コメや鶏卵価格上昇(12月24日) 農林水...
-

主食のコメ廃棄に歯止め フィリピン 大統領令準備、年280万人分相当 ...
フィリピン農業省は主食のコメの廃棄に歯止めをかける。年280万人分に相当するこ...
-
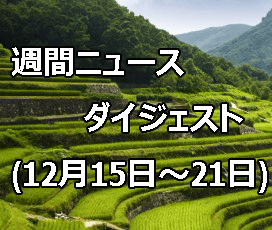
年収の壁123万円決定 手取り増、学生の制限緩和 週間ニュースダイジ...
▼英、TPP加盟が発効 12カ国体制で自由貿易推進(12月15日) 英国の環...
-

高冷地でコメ栽培に挑戦 「有機大国」リヒテンシュタイン
(啓発機構ウェルタッカーの見本農場=ファドゥーツ) 栽培適地とは言えない欧州中...

 ツイート
ツイート