「研究紹介」 支店の存在意義を欧州の事例で考える 農林金融4月号から
2021.04.11
チケット販売大手の「ぴあ」が全支店廃止を決めた。中高年層の人にとっては感慨深いに違いない。舞台やコンサートなどの人気チケットは並んで買うものだったし、ぴあの店舗の有無は人が集まる場所かどうかの基準でもあった。最盛期の1990年代には全国に600店以上展開していたが、インターネットを通じたチケット販売が主流になり、新型コロナウイルスの感染拡大でイベントの中止が相次ぎ、残っていた77店舗の廃止に追い込まれた。
同じようなことが金融機関の支店で起きても不思議ではない。農林中金総合研究所の「農林金融」2021年4月号の「デジタル化で近接性を高めようとする欧州の金融機関」で、髙山航希主事研究員は「デジタリゼーションが必要なのは、協同組織金融機関など、地域に根付く金融機関も例外ではない。(中略)しかしその一方で、こうした金融機関は、デジタル化を進めることで、地域や人との近接性を基礎とする利用者との関係が崩れてしまうのではないか、という葛藤も同時に抱えている」と問題提起する。
論文は、欧州の DZバンク(ドイツ)、クレディ・アグリコル(フランス)、KBCグループ(ベルギー)の支店運営をみることで、デジタル化への対応を考える。DZバンクでは、アドバイザーが消費者金融の利用など家計診断をしている。クレディ・アグリコルは、顧客の資産形成を職員がアドバイスする。ベルギーのKBCは、店舗やオンラインを含む各チャネルで得た顧客や取引の情報を相互に利用する総合的な戦略を進めている。
いずれもデジタル技術によって、店舗職員と顧客のコミュニケーションを効率化・高度化し、サービスを顧客個別にカスタマイズして提供することで、近接性を高めようとしている。高度な顧客対応ができる能力の高い職員を配置しなければ、デジタル技術の単純な導入だけでは支店の存在意義がなくなると示唆する内容だ。
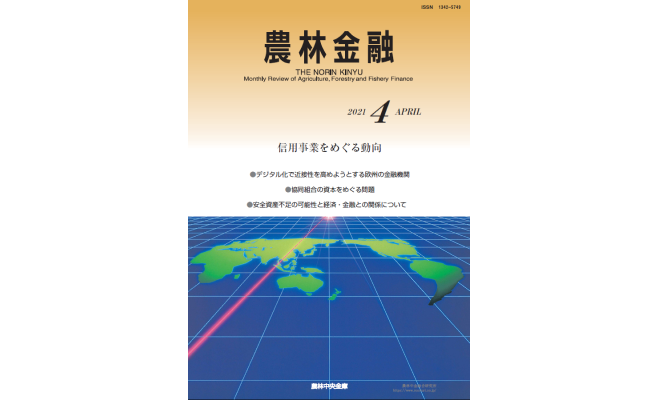

 ツイート
ツイート