フードテック考 鬼頭弥生 農学博士 連載「口福の源」
2024.11.11

持続可能な食料の生産・流通・消費を目指す方向性の中で、「フードテック」としてさまざまな技術が開発されつつある。中でもしばしば話題となるのは、生産にかかる環境負荷の大きい肉類の代替となるタンパク質の生産・製造技術である。(画像:心に浮かぶのは恐怖か嫌悪か好奇心か、筆者画)
一口に代替タンパク質といっても、多様な原料・製法の技術が存在する。開発や市場導入のどの段階にあるかはそれぞれ異なるが、大豆ミートなどの植物由来の「プラントベース」食品、昆虫食、動物由来の細胞を培養することによる「培養肉」(「細胞性食品」と呼ばれることもある)、微生物による物質生産(精密発酵)など、実にさまざまである。その性質やそこから想起されるイメージに応じて、消費者における受け止めもさまざまであることが予想される。
「フードネオフォビア(食物新奇性恐怖)」という言葉がある。P・プライナー博士らによる1992年の論文に従えば、新奇な食べ物(novel food)に対して食べることを躊躇(ちゅうちょ)したり、避けたりすることをいう。こうした恐怖心は、自分に害を及ぼすかもしれない食環境への防御機能として人間(あるいは動物)に備わったものと言えるのだが、フードテックのような新技術に対して防御する方向に働く可能性がある。
フードネオフォビアとは別に、種々のタイプの嫌悪感もまた、新技術を拒絶する方向に働く。J・ハイド博士とP・ロジン博士らが97年に発表した論文によれば、嫌悪感は汚れの観念に特徴付けられ、中核的嫌悪、動物性想起の嫌悪、社会道徳性嫌悪の3側面があるという。さらに、人々は人為的に感じられる食品についてリスクを高く見積もる傾向があり、その性向もまた技術の受け止めを躊躇するよう働く。
他方で、新技術を肯定的に受容する方向に作用する要因もある。人々の持つ好奇心は新しいものを試す動機付けになるし、経験や馴染(なじ)みが増せば新奇性恐怖が薄れると予想できる。そのほか、科学への信頼やリスク︱ベネフィットの認知も複雑に絡んだ結果として、新技術に対する個々人の態度が形成されるだろう。
こうした人々の認知・感情を目の当たりにすると、技術推進側の視点では、「どうすれば受容されるか」とか、「悪いイメージを払拭するにはどうするか」とか、「行動変容を起こすには」という話になることが多い。確かにそうした方略が求められる局面もあるかもしれない。しかしながら、新技術導入の目的が倫理的観点から重要かつ正当なものであったとしても、それに至るプロセスも正当であらねばならないと思われる。たとえまわり道に見えるとしても、結論ありきではない消費者を含めた関係者間の対話と、対話に必要なリスク評価などの手続きと情報共有が、まずは重要になるのではないだろうか。
(Kyodo Weekly・政経週報 2024年10月28日号掲載)
最新記事
-
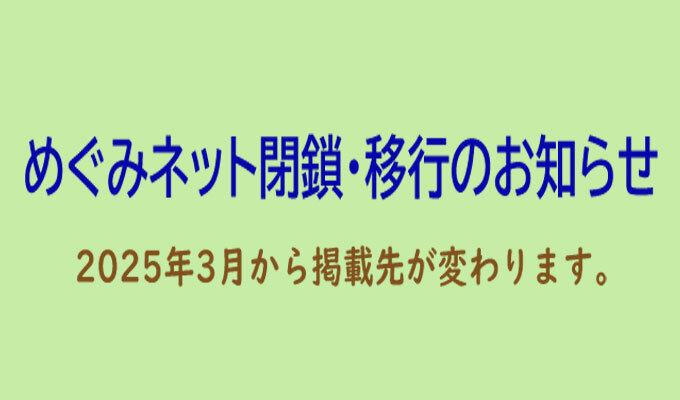
めぐみネット閉鎖・移行のお知らせ
めぐみネットは開設以来、多くの皆さまにご利用いただきましたが、食農分野の情報を...
-

訪日消費、初の8兆円超 週間ニュースダイジェスト(1月12日~1月1...
▼稲作の新たな栽培方法に大賞 高校生ビジネスコンテスト(1月12日) 全国の...
-
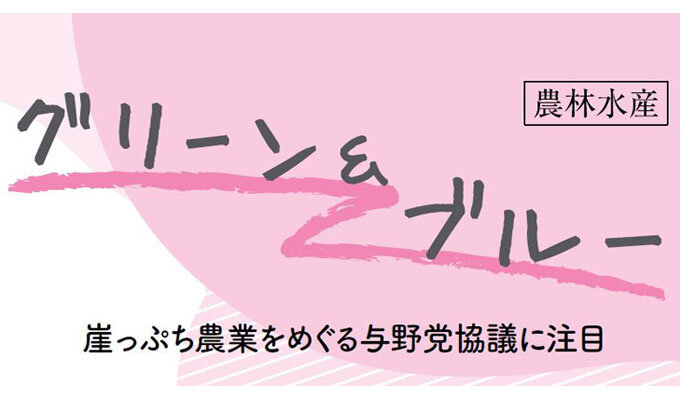
崖っぷち農業をめぐる与野党協議に注目 小視曽四郎 農政ジャーナリスト...
政府の2024年度補正予算案は、28年ぶりに衆院で野党の修正要求をのんで成立す...
-

豪でも鳥インフル猛威 供給不足で卵の購入制限続く
鳥インフルエンザの感染拡大などによる鶏卵不足から、オーストラリアではスーパーマ...
-

日本食店数3%増で過去最大 タイ 成長は鈍化、総合和食が1位に NN...
日本貿易振興機構(ジェトロ)バンコク事務所は1月8日、タイで営業する日本食レス...
-

食品輸出促進で稼ぐ力強化 週間ニュースダイジェスト(1月5日~1月1...
▼大間マグロに2億円 2番目高値、豊洲で初競り(1月5日) 東京都江東区の豊...
-

予算膨張115兆円超え 25年度、歳出・税収最大 週間ニュースダイジ...
▼農業総産出額2年連続増 23年、コメや鶏卵価格上昇(12月24日) 農林水...
-

飲み会対策教えます 安武郁子 食育実践ジャーナリスト 連載「口福の...
年末年始は飲み会やパーティーが増える季節ですね。楽しい時間を過ごす一方で、歯や...
-

ふるさと納税の功罪 沼尾波子 東洋大学教授 連載「よんななエコノミ...
年末を迎え、ふるさと納税の返礼品をめぐる「商戦」が活発化している。ふるさと納税...
-

米ナスに懸ける20年間の生産者の努力 青山浩子 新潟食料農業大学准教...
あるレシピ検索サイトで、検索用語の首位が「簡単」から「ナス」に変わったというニ...

 ツイート
ツイート