古き良き相棒と海を越える 連載「旅作家 小林希の島日和」
2024.08.05

街に暮らしていると、船(定期船)を公共交通機関だと認識する人は少ないのではないかと思う。
私もしかり。島旅を始めて、日本にこれほど多くの船会社があるのかと驚いた。日本旅客船協会に所属している船会社だけで、離島航路の船会社を含めて約500社もある。
船に着目すると、そこから港のあり方や島を取り囲む海の特徴など、広い視野で地域が見えてくるのが面白い。
例えば、瀬戸内海の島々を運航するカーフェリーは、船体が吹き抜けになった造りをしているものが多い。穏やかで凪(な)いだ瀬戸内海では、走航中に波が船内に入ってくることがめったにないので、吹き抜け構造にして船体を軽くしている。
港によく浮桟橋や可動式桟橋が用いられているのは、瀬戸内海は1日の干満差が大きいから。古い港では、雁木(がんぎ)(階段状の桟橋)が見られ、風情を醸し出している。
香川県の讃岐広島に毎月通っていた頃、船舶免許を取得した。いざ操船すると、潮流が複雑だったり、岩礁が多くあったりして、「毎日練習しないと、操船は無理!」と悟った。以前、船員教育を行っている学校である海技教育機構で、「船は、風、波、潮といった自然を理解しなければ乗りこなせない乗り物なので、現代でも帆船を使った訓練をしている」と聞いた。
古来、日本人は船を使い、外の地域と交流や交易をしてきた民族だ。操船や造船の技術があったのは、自然をよく理解していた証しだ。
静岡県沼津市の愛鷹(あしたか)山麓にある3万8千年前の地層から、神津島(こうづしま)産の黒曜石の石器が発見されている。石器時代には、東京都心の南方180キロに位置する伊豆諸島の神津島と本州を航海していたようだ。
いったい、どんな船に乗っていたのだろう。縄文時代の遺跡から丸木舟が出土しているが、さらに古くは葦舟(あしぶね)とも考えられている。「古事記」や「日本書紀」には、日本を「豊葦(とよあし)原之瑞穂国(はらのみずほのくに)」と記している。「葦が茂り、稲穂がみずみずしく育つ、豊かな国」が、古代の日本だったとすれば、葦を使った舟も身近にあったのかもしれない。
近年は過疎高齢化で、離島航路の乗船者は減少し、航路の廃止や減便といった課題に直面している。当然、港も閑散として、少し寂しい。全国的に船員も減少している。
島へ向かう時、先人と共に歩んできた船の歴史や海に繰り出した彼らの勇気に、たびたび思いを重ねるようになった。
(Kyodo Weekly・政経週報 2024年7月22日号掲載)
最新記事
-
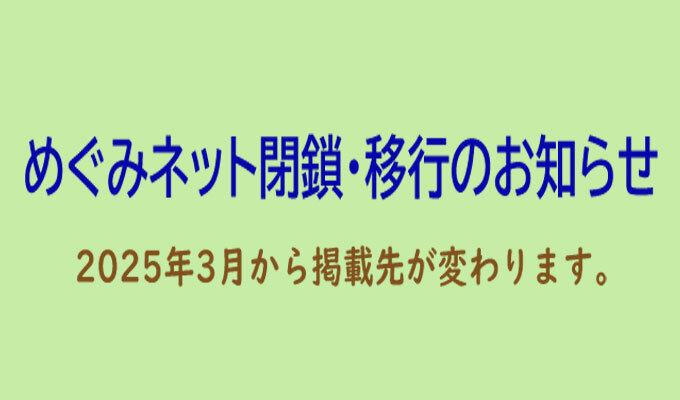
めぐみネット閉鎖・移行のお知らせ
めぐみネットは開設以来、多くの皆さまにご利用いただきましたが、食農分野の情報を...
-

訪日消費、初の8兆円超 週間ニュースダイジェスト(1月12日~1月1...
▼稲作の新たな栽培方法に大賞 高校生ビジネスコンテスト(1月12日) 全国の...
-

地方創生2.0に期待すること 藤波匠 日本総合研究所調査部上席主任研...
9月の自民党総裁選で石破茂新首相が選出されて以来、地方創生が再び政治課題の俎上...
-
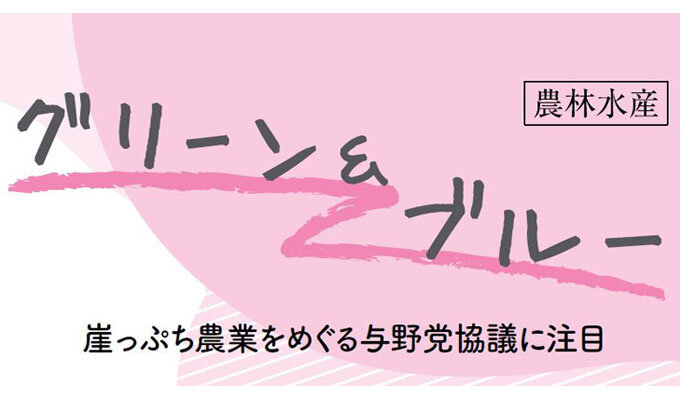
崖っぷち農業をめぐる与野党協議に注目 小視曽四郎 農政ジャーナリスト...
政府の2024年度補正予算案は、28年ぶりに衆院で野党の修正要求をのんで成立す...
-

食品輸出促進で稼ぐ力強化 週間ニュースダイジェスト(1月5日~1月1...
▼大間マグロに2億円 2番目高値、豊洲で初競り(1月5日) 東京都江東区の豊...
-

予算膨張115兆円超え 25年度、歳出・税収最大 週間ニュースダイジ...
▼農業総産出額2年連続増 23年、コメや鶏卵価格上昇(12月24日) 農林水...
-

生きる力学べる港町 中川めぐみ ウオー代表取締役 連載「グリーン&...
「食を通して『生きる力』を学ぶ交流学習」。福井県小浜市の阿納(あの)という総人...
-

飲み会対策教えます 安武郁子 食育実践ジャーナリスト 連載「口福の...
年末年始は飲み会やパーティーが増える季節ですね。楽しい時間を過ごす一方で、歯や...
-

ふるさと納税の功罪 沼尾波子 東洋大学教授 連載「よんななエコノミ...
年末を迎え、ふるさと納税の返礼品をめぐる「商戦」が活発化している。ふるさと納税...
-

米ナスに懸ける20年間の生産者の努力 青山浩子 新潟食料農業大学准教...
あるレシピ検索サイトで、検索用語の首位が「簡単」から「ナス」に変わったというニ...

 ツイート
ツイート