和食を科学で味わう 畑中三応子 食文化研究家 連載「口福の源」
2024.01.29

東京・上野の国立科学博物館で開催中の特別展「和食 日本の自然、人々の知恵」は、食文化を科学で料理するユニークな展覧会である。
展示は「和食って何?」という問いかけから始まる。科学的な切り口が最も冴(さ)えるのが、日本の自然と食材、和食の関係をひもとく第2章である。南北に長い日本列島は世界でも有数の生物多様性を持つ。日本と同様に、大陸のそばにある島国のイギリス、ニュージーランドと比較すると、その差は圧倒的だ。
日本には4500種類近くもの魚類が生息するのに対し、イギリスは300種類程度と少なく、ニュージーランドでも1300種類弱しかいない。7500種類を超える植物が自生し、うち千種以上が食用にできる日本に対し、イギリスは1600種類、ニュージーランドは2千種類程度である。
和食がユネスコ無形文化遺産に登録された時、特徴として地域に根ざした食材が豊富なことが挙げられたが、こうして数字で示されると説得力がぐっと増す。さまざまな生物がいるから、食材も多くなる。世界で最も多くの魚介類を活用している食文化として、会場に多数展示される魚や貝の実物大模型は圧巻。模型なのに見るだけで食欲が刺激されてしまった。
和食の基本である「だし」と「うま味」は、水質と深く関係する。国土の7割が山地の日本は地形が急峻(きゅうしゅん)で、降水量が多い。雨水や雪解け水に土壌のミネラル分が溶け込む時間がなく、早急に海へ流れ出るため軟水になる。ヨーロッパなど大陸の地形は平坦で、雨水の滞留時間が長くゆっくりミネラル分が溶け込むため硬水になる。軟水は、昆布、干し椎茸(しいたけ)、かつお節のうま味成分を効果的に抽出することから、和食のだし文化が確立した。
一方、硬水のミネラル分は動物性たんぱく質と結合してアクになるので、肉の調理に適している。フランスで修業したシェフに、同じレシピでブイヨンを取っても思う味にならず、仕方なくフランス製ミネラルウオーターを使ったことを聞いた。洋の東西を問わず、水は味の根幹なのである。
昆布は水のミネラル分が少ないほど、うま味がよく出る。ごく軟水の京都で昆布だし中心の食文化が発達した理由は、そこにある。海に生えている状態そのままの標本を眺め、よくこんなワイルドな海藻から洗練されただしを生み出したものだと、ご先祖の創意工夫に感謝した。日本人は海藻を消化できる腸内細菌を持っているそうだ。
展示の残り半分は、縄文時代から現代までをたどる歴史編。江戸期の料理の再現模型と出典の料理書がセットで展示されるなど、目でも楽しめる構成になっている。
和食イラストのマスキングテープや海藻コースターなど、特設ショップにオリジナルグッズが多彩なのも楽しい。2月25日の終了後は、4月の山形・鶴岡市を皮切りに来年にかけて全国を巡回する。
(写真:土中の様子と生え方の違いが分かる多種多様な地ダイコンのレプリカ。上段の左から2番目が世界最大品種の桜島ダイコン)
(Kyodo Weekly・政経週報 2024年1月15日号掲載)
最新記事
-
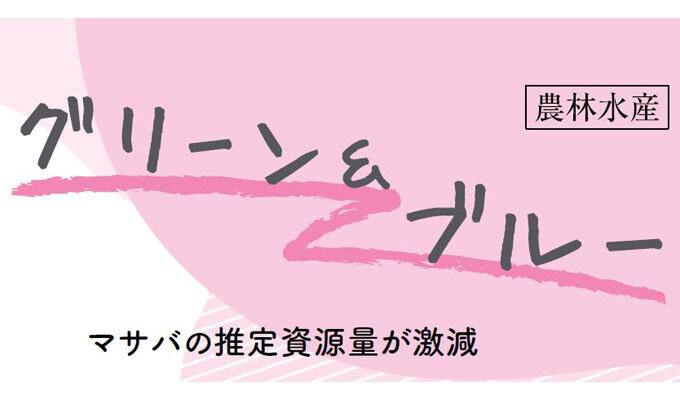
マサバの推定資源量が激減 佐々木ひろこ フードジャーナリスト 連載...
塩焼き、みそ煮、竜田揚げ、シメサバ、南蛮漬け...。定番の家庭料理に人気のサバ...
-
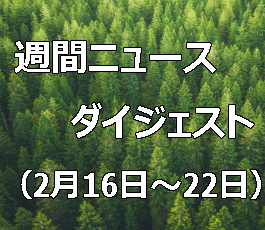
コメ伸び率70%、過去最大 1月物価3.2%上昇 週間ニュースダイジ...
▼原発回帰、再エネ最大5割 温暖化対策で脱炭素推進(2月18日) 政府は国の...
-

少子化で変化する大学の役割 藤波匠 日本総合研究所調査部上席主任研究...
先日、大学入学共通テストが実施されました。志願者数は50万人に少し欠ける49万...
-
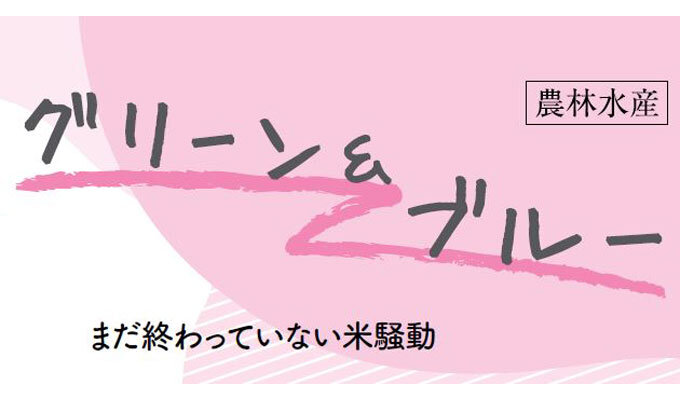
まだ終わっていない米騒動 小視曽四郎 農政ジャーナリスト 連載「グ...
真冬だというのに米業界が熱い。雪をも溶かさんばかりに数値が過去最高の記録づくめ...
-

日本産食品、輸入が過去最高 ベトナム 24年24%増、ホタテ100億円...
日本の農林水産省によれば、2024年のベトナムの日本産農林水産物や食品の輸入額...
-
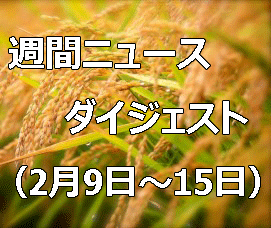
備蓄米3月下旬から店頭 高騰に対処、最大21万トン 週間ニュースダイ...
▼経常黒字、最大29兆円 24年、2年連続増加(2月10日) 財務省が発表し...
-

食いねえ!現代版〝寿司屋台〟 中川めぐみ ウオー代表取締役 連載「...
"本格寿司(すし)のキッチンカー"。全国的にも珍しいこの業態にチャレンジするの...
-

「そらいろコアラ」の距離と時間 沼尾波子 東洋大学教授 連載「よん...
地方新聞47紙とNHK、共同通信社が地域活性化の取り組みを表彰する第15回地域...
-

九州大学発の新興カイコ、ベトナムでブタ用ワクチン大規模実証 NNA
蚕を活用したワクチンを開発する九州大学発の新興企業KAICO(カイコ、福岡市)...
-
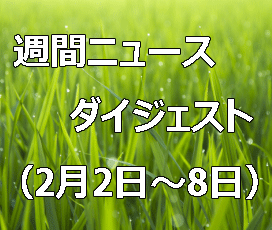
農産物輸出初の1.5兆円 週間ニュースダイジェスト(2月2日~2月8...
▼農産物輸出初の1.5兆円 24年、12年連続で過去最高(2月4日) 農林水...

 ツイート
ツイート