問われる給食の「チカラ」 試食会が入り口に 共同通信アグリラボ編集長 石井勇人
2023.09.27

学校給食の無償化を実施する自治体が増える中、試食会を通じて給食の意義を問い直す動きが注目されている。無償化は、子育て支援策の一つとして位置付けられているが、財政負担が重く、導入する前提として給食が果たす役割について幅広い理解を深めることが重要だ。
群馬県みなかみ町は9月21日、新治(にいはる)小学校に町長、教育長、町議会議長、PTA会長、食材を提供した生産者らを招き、5年生の児童と対面する形で給食をともにした。阿部賢一町長(写真中央)は「体に良いものを食べるよう心がけ、生まれ育った所でこんなにおいしいものができることを知ってほしい」と児童に語りかけた。

この日のメニューは、ギョーザ、野菜のキムチあえ、トマトかき玉スープ、白飯、飲むヨーグルト。デザートに巨峰が付き、食材の約8割が地元産だ。同じメニューの給食を約1600食用意し、町内の全ての小中学校と保育施設で提供した。

主菜のギョーザは、地元特産のシイタケ、マイタケ、エノキをみじん切りにして包んで揚げ、香味ソースで味付けした。地元の利根商業高校2年の川端希歩(のあ)さんが考案し、キノコ料理の全国コンクールで最優秀賞(林野庁長官賞)に選ばれたオリジナルレシピ-を給食向けに再現した。

ゲストとして招かれた林野庁の塚田直子特用林産対策室長は、黒板に「一日一蕈(ジン)」と書いて、毎日キノコを食べると健康に良いとアピールした。キノコの臭いや食感が苦手な児童も2人いたが、「今日は大丈夫だった」と完食した。同校の信澤由佳栄養教諭は「給食には力がある。(給食で)苦手なものを乗り越えることができ、それが子どもの自信につながる」と給食が果たす役割を説明した。
児童から、キノコについて質問を受けた鈴木八一郎・鈴木まいたけ園代表取締役は「以前、マイタケは山でしか採れず、見つけると舞い上がるほど珍しくてマイタケと呼ばれるけれど、栽培できるようになり、出荷まで約3ケ月かかる」と丁寧に答えた。

(鈴木まいたけ園の栽培施設)
児童は「みなかみ町に住んでいるとこんなにおいしいものが食べられて幸せです」、「地元の食材をもっと食べたいと思った」などと喜んだ。給食には、食育、地産地消、伝統や文化など地域の誇り、生産や加工に対する学び、給食に関わる人たちへの感謝、地域に暮らす人との結び付きなど、様々な意義がある。
みなかみ町は、地元産の食材にこだわった給食を毎年1回提供しており、コロナ禍による中断を挟んで今回が8回目。これとは別に年2回、町民が参加する試食会を開くなど給食に対する理解を深めてもらう取り組みを進めてきた。半年前から第3子以降の給食費を無償にしたが、本格的な導入は検討中だ。

学校給食の費用は、施設・設備の経費・運営費は学校の設置者(自治体)、食材などそれ以外の経費は保護者の負担と、学校給食法が定めているが、子育て支援や移住・定住の促進のため、無償化する自治体が増えている。特に2022年度は、新型コロナウイルス感染症の対策として地方創生臨時交付金を使って導入する自治体が急増した。
ただ、財源の制約から「第3子から対象」「半年間」など条件付きの自治体も多い。無償化を恒久実施するためには、交付金に代わる安定的な財源を確保しなくてはならない。今年3月20日に自民党の茂木敏充幹事長が「小中学校の給食費無償化を実現したい」と述べたが、6月13日に政府がまとめた「こども未来戦略方針」では、「学校給食の実態調査を速やかに行い、1年以内にその結果を公表する(中略)給食実施状況の違いや法制面等も含め課題の整理を丁寧に行い、具体的方策を検討する」という記述にとどまった
また、地域によって給食の事情は大きく異なっている。地元産や有機栽培の農産物など食材にこだわる自治体が増える一方、主食・おかず・牛乳がそろった「完全給食」さえ実施できない地域や学校もある。小中学校の統廃合を受けて一カ所で調理し複数の学校に配達する「センター方式」が主流になる中、学校の敷地に給食施設を備え、手作りの温かい食事を提供できる「自校方式」を維持する自治体もある。
給食には様々な価値があり、限られた財源を完全給食の徹底や給食の質の向上に使うのか、無償化に使うのかなど、「どんな給食を目指すのか」という地域住民の合意形成が不可欠だ。(文・写真 共同通信アグリラボ編集長 石井勇人)
最新記事
-
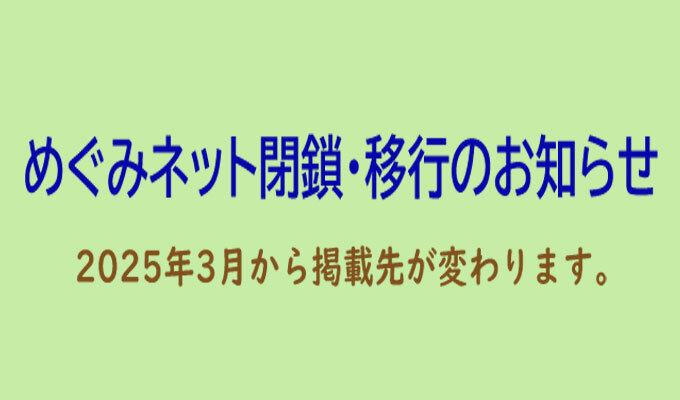
めぐみネット閉鎖・移行のお知らせ
めぐみネットは開設以来、多くの皆さまにご利用いただきましたが、食農分野の情報を...
-

訪日消費、初の8兆円超 週間ニュースダイジェスト(1月12日~1月1...
▼稲作の新たな栽培方法に大賞 高校生ビジネスコンテスト(1月12日) 全国の...
-

地方創生2.0に期待すること 藤波匠 日本総合研究所調査部上席主任研...
9月の自民党総裁選で石破茂新首相が選出されて以来、地方創生が再び政治課題の俎上...
-
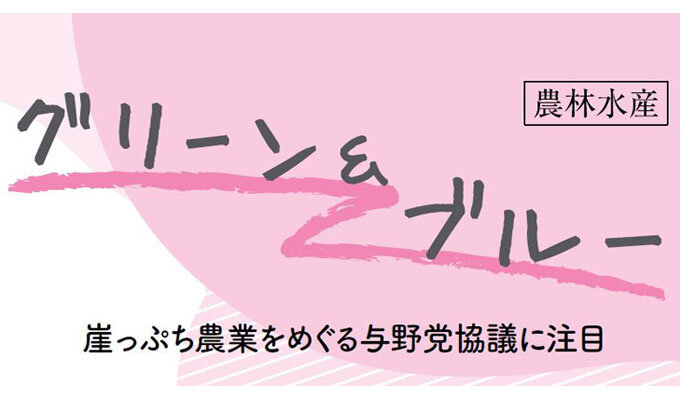
崖っぷち農業をめぐる与野党協議に注目 小視曽四郎 農政ジャーナリスト...
政府の2024年度補正予算案は、28年ぶりに衆院で野党の修正要求をのんで成立す...
-

食品輸出促進で稼ぐ力強化 週間ニュースダイジェスト(1月5日~1月1...
▼大間マグロに2億円 2番目高値、豊洲で初競り(1月5日) 東京都江東区の豊...
-

予算膨張115兆円超え 25年度、歳出・税収最大 週間ニュースダイジ...
▼農業総産出額2年連続増 23年、コメや鶏卵価格上昇(12月24日) 農林水...
-

生きる力学べる港町 中川めぐみ ウオー代表取締役 連載「グリーン&...
「食を通して『生きる力』を学ぶ交流学習」。福井県小浜市の阿納(あの)という総人...
-

飲み会対策教えます 安武郁子 食育実践ジャーナリスト 連載「口福の...
年末年始は飲み会やパーティーが増える季節ですね。楽しい時間を過ごす一方で、歯や...
-

ふるさと納税の功罪 沼尾波子 東洋大学教授 連載「よんななエコノミ...
年末を迎え、ふるさと納税の返礼品をめぐる「商戦」が活発化している。ふるさと納税...
-

米ナスに懸ける20年間の生産者の努力 青山浩子 新潟食料農業大学准教...
あるレシピ検索サイトで、検索用語の首位が「簡単」から「ナス」に変わったというニ...

 ツイート
ツイート