「食べられる容器」に脚光 価値付加し脱プラスチック 前田佳栄 日本総合研究所創発戦略センターコンサルタント
2023.01.09

近年、海洋プラスチックごみの問題が大きく取り上げられている。海洋プラスチックごみに関しては、海洋環境の悪化や海岸機能の低下、景観への悪影響、船舶航行の障害、漁業や観光への影響などが懸念されており、特に、一般に5㍉以下の微細なプラスチック類を指す「マイクロプラスチック」による海洋生態系への影響は世界的な課題となっている。
国内では2021年6月に「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が成立した。この法律では、製品の設計から廃棄物の処理まで全ての過程で、プラスチックの資源循環の取り組みを促進するための措置が盛り込まれている。カーボンニュートラルのトレンドを含め、多くの企業が「脱プラスチック」に向けた取り組みを進めている。(写真はイメージ)
食品関連企業では、包装容器やフォーク・スプーンなどの脱プラスチックが進んでいる。包装容器の軽量化や形状変更によりプラスチック使用量を削減する、バイオマスプラスチックや再生プラスチックを利用する、プラスチック製に代えて紙製のストローや木製のフォークを採用するといった取り組みを行う企業が増えている。
脱プラスチックに向けて、脚光を浴びているのが「食べられる容器」である。菓子メーカーの桔梗屋(山梨県笛吹市)では、餅を入れるカップと蓋をモナカに変更した「桔梗信玄餅 極」が人気を集めている。また、源吉兆庵ホールディングス(岡山市)では、国産米粉と砂糖のみを原料とする堅焼き煎餅のスプーンを開発した。食品に含まれる水分によって容器が柔らかくなってしまうなどの課題があり、耐久性確保のノウハウが重要となっている。
食べられる容器の普及にむけた課題の一つがコストである。安価なプラスチックと同程度まですぐにコストを下げることは難しく、商品価格が上がってしまうことも予想される。
ただ、これらの容器の「食品」という側面を生かすことで、単なるプラスチックの代替品ではなく、プラスチックとは異なる付加価値をもつ商品とすることも可能である。例えば、食感やフレーバーを変える役割を持たせる、カルシウムや鉄分などの栄養素を加えるなどが候補となる。既に発売されている類似商品では、フレーバーを加えたマドラー型の飴などがあり、飴を溶かしながら紅茶などを飲むことで、味の変化を楽しめる商品となっている。
また、見た目の良さも重要になる。原料を変えることで色のバリエーションを増やすなど、SNS映えを意識した工夫も有効である。付加価値を認め、従来よりも高い値段でも買いたいと思えるような工夫が、環境対応の推進力となるのである。
(Kyodo Weekly・政経週報 2022年12月26日号掲載)
最新記事
-

石川・能登地方で震度7 週間ニュースダイジェスト(12月31日~1月...
▼18歳成人、最少106万人 少子化影響、総務省推計(12月31日) 総務省が公表した2024年1...
-
地方発の新たな応援スタイル #甲府にチカラを 藤波匠 日本総合研究...
サッカーJリーグのヴァンフォーレ甲府が、アジアチャンピオンズリーグ(ACL)で熱戦を繰り広げていま...
-
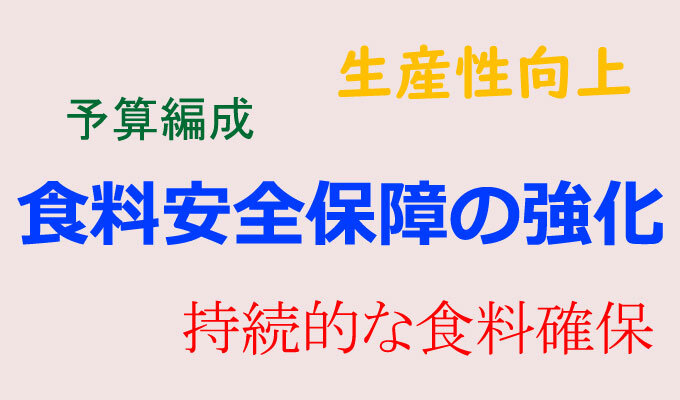
食料安保論議、従来思考を改める時 小視曽四郎 農政ジャーナリスト ...
食料供給の有事法制化で、国から増産を求められた農家らが達成できなかった場合、罰金は科さないが事業者...
-

分散備蓄を食料安保の柱に 震災の教訓生かそう アグリラボ編集長コラム
(写真はイメージ) 能登半島地震に続いて羽田空港で飛行機の衝突事故が起き、気の毒で残念な年明けとな...
-
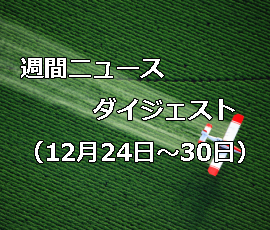
農業技術革新へ認定制度 政府、開発目標策定 週間ニュースダイジェスト...
▼政策正常化の利点強調 日銀総裁「最大限活用を」(12月25日) 日銀の植田和男総裁が東京都内で開...
-

福祉施設発、魅惑の雑貨ショップ 沼尾波子 東洋大学教授 連載「よん...
長崎県東彼杵(ひがしそのぎ)町には、若い世代が農協の倉庫跡地を爽やかにリノベーションした「ソリッソ...
-
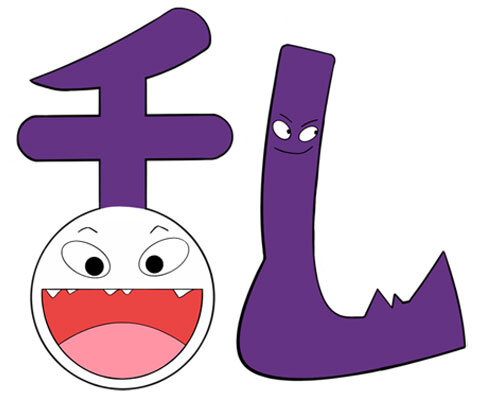
しっかり噛んで年越しを 安武郁子 食育実践ジャーナリスト 連載「口...
年末年始は、外食の機会が増え、食べ過ぎや飲み過ぎが気になる時期ですね。今回は、漢字の「乱」をテーマ...
-
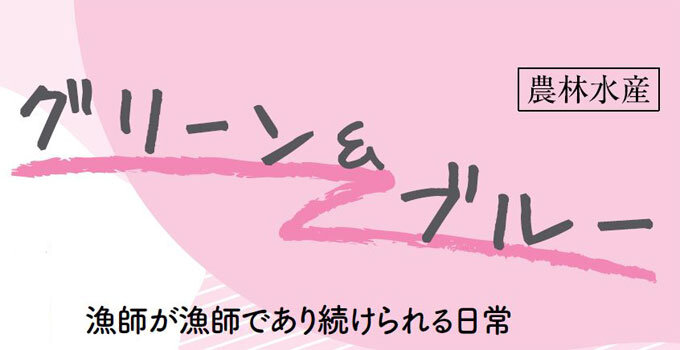
漁師が漁師であり続けられる日常 中川めぐみ ウオー代表取締役 連載...
「私たちが欲しいのは、お金でなく町の活力。漁師が漁師であり続けられる日常です」 これは和歌山県すさ...
-

立ち飲みおにぎりの新業態 中国・広州で戦う日本人シェフ NNA
日本食店がひしめく広東省広州市の天河区に、"立ち飲みおにぎり"というユニークな業態の店が誕生した。...
-

賃上げ重点112兆円予算 3割借金、国債費最大 週間ニュースダイジェ...
▼食料安保2新法提出へ 緊急増産とスマート農業(12月18日) 政府が食料安全保障の強化に向け、2...

 ツイート
ツイート