DXで加工・流通の合理化を 「みどりの食料システム戦略」を考える 前田佳栄 日本総合研究所創発戦略センターコンサルタント
2021.05.17

(写真はイメージ)
SDGs(Sustainable Develop ment Goals:持続可能な開発目標)とは、2015年9月の国連サミットにて全会一致で採択された、誰一人取り残さない(leave no one behind)持続可能でよりよい社会の実現を目指す世界共通の目標である。
2030年を達成年限とし、貧困や飢餓などの社会面、エネルギー・資源の有効活用や不平といった是正などの経済面、気候変動などの環境面の3側面から17のゴールが掲げられている。
最近ではメディアで取り上げられる機会も増え、企業経営において重要な観点の一つとなっている。
農林水産物・食品の輸出額の増加、スマート農業の普及による生産性の向上といった、明るい兆しが見えてきた日本の農業だが、担い手の確保、気候変動への対応など、まだまだ課題は山積している。
このまま気候変動が進行すれば、農業生産が不安定化し、農業が途絶えてしまう地域が出てくる可能性すらある。人間が生きていく上でなくてはならない「食」を支えている農業こそ、持続可能な産業でなくてはならない。
最先端の技術に目を向けると、農業はデジタルトランスフォーメーション(DX)やバイオなどの分野で目覚ましい発展を遂げている。危機を前に立ちすくむのではなく、こうした技術の発展をチャンスと捉え、新たな農業の姿を探求していかなくてはならない。
欧米追い戦略策定
欧米では、持続可能な農業の実現に向けた戦略策定の動きがみられる。欧州連合(EU)は、農場から食卓までを意味する「ファーム to フォーク戦略」を2020年5月に発表した。
具体的には、農薬の使用およびリスクの50%削減、1人当たり食品廃棄物の50%削減などの意欲的な目標が設定されている。
米国の農務省は2020年2月に農業イノベーションアジェンダを公表し、2050年までの農業生産量の40%増加と環境フットプリント(製品や企業活動が環境に与えている負荷を評価するための指標)の50%削減の同時達成を目標に掲げている。
世界的に環境負荷の小さい農業が主流になっていく中で、従来のやり方だけでは特に輸出時などに影響が出る可能性もある。ファーム to フォーク戦略では、EUフードシステムをグローバル・スタンダードとすると記載されており、世界の状況を見ながら生産方法を改善していくことが求められる。
日本でも同様に、農林水産省にて持続可能な農業の実現に向けて、新たに「みどりの食料システム戦略」の策定が行われ、2021年3月に中間とりまとめを行い、5月までに策定の予定である。(注:記事執筆は4月。同省は5月12日に策定、発表した)
みどりの食料システム戦略は、生産から消費のサプライチェーン(調達・供給網)の各段階でカーボンニュートラルなどの環境負荷軽減につながる技術革新を促し、生産力向上と持続性の両立を図ることを目指したものである。(下図:農水省資料より)

具体的な取り組みとしては①調達=資材・エネルギー調達における脱輸入・ 脱炭素化・環境負荷軽減の推進、②生産=イノベーションなどによる持続的生産体制の構築、③加工・流通=ムリ・ムダのない持続可能な加工・流通システムの確立、④消費=環境にやさしい持続可能な消費の拡大や食育の推進といった柱が挙げられている。
本稿では加工・流通の面に注目する。
生産現場だけではなく、流通や消費の段階でも課題は尽きない。新型コロナウイルスの流行により流通や消費が大きく変わったことで、打撃を受けている農業者は少なくない。学校給食の中止により、牛乳の大量廃棄の危機が発生したことは記憶に新しい。
今冬は生産が好調だったために市場が飽和し、農産物の価格の低下が目立った。
筆者は立派なハクサイが2玉で200円という破格の値段で販売されているのを目にして衝撃を受けた。消費者にとってはありがたい話かもしれないが、生産者にとっては、販売価格の低下は死活問題である。
みどりの食料システム戦略では、加工・流通面の取り組みとして「データ・AI(人工知能)の活用による加工・流通の合理化」が挙げられている。
しかし、今求められているのは合理化だけではない。農業者の試行錯誤を付加価値として実需者・消費者に理解してもらうための仕組みが不可欠である。今回は、そのための方法を「規格」に焦点を当てて考える。
指標の精密化で選択しやすく
農産物の規格は大きさや形・傷を指標に「S・M・L」「優・秀・良・可」といった段階で大別されている。
規格を絞ることによって、実物を確認しなくても値付けができ、取引を容易にする意味があるが、その一方で、規格から外れたものは、味や安全性に問題がないものであっても急に価値が下がってしまうという課題があった。
デジタル化の恩恵によって、従来よりも農産物一つずつにより多くの情報を付与できるようになってきた。
ポイントとなるのが、規格の構成要素とメッシュを飛躍的に増やすことで、農産物の価値を正確に表現できる点である。例えば、選別の際に、画像認識を活用して傷の度合いや曲がり具合などを数値化して指標とすることができる。
消費者の中には、自宅で普段使うものであれば多少傷や曲がりがあっても気にせず、鮮度の高さや味の良さを重視するという人も少なくない。輸送過程での効率や腐敗のリスクなどは考える必要があるが、多様化する消費者ニーズを捉えることができれば、農業者の収益機会の向上やフードロスの削減につなげることが可能である。
化学肥料や化学農薬の使用に関して、現在は基準量以下に抑えることが求められているが、基準量からどの程度削減できているかについては適切に表現されている、とはいいがたい。
化学的に合成された肥料および農薬などを使用しない有機栽培か、一定の基準まで使用量を削減した特別栽培という制度があるが、1項目でも基準に満たなければ一般のものと同じ評価を受けることとなってしまう。そうした枠に入らない場合でも、散布量・散布回数などを段階的に評価できるような枠組みを設けることによって、消費者がその価値を理解できるようになる。
このほかにも、産地、品種、味、鮮度、ビタミンや機能性成分などの含有量など、消費者に訴求できる価値はさまざまだ。
さらに、環境への影響を示す「エコ度」や、新規就農者や地域の特産品の支援のための「地域貢献度」といった指標も加えることも有効である。見た目や価格を重視して選んでいた消費者でも、こうした情報があれば、これまでと違う観点で農産物を選ぶことができる。
ただ、情報が無限に増えてしまうと、選びにくくなるデメリットもあるため、適切な情報提供を行う工夫も重要である。
一気通貫の改革が重要
情報の流れは、生産→流通→消費の一方通行ではない。消費者からフィードバックを受けることにより、サプライチェーンの上流も、パワーアップすることができる。
従来は、農業者は自分が生産した農産物がどのように消費され、評価されたのかはブラックボックスとなっていたが、規格のバリエーションを増やすことにより、どのような農産物が人気を集めているのかが一目瞭然で分かるようになる。
より消費者に受け入れられる農産物を生産するためには、その消費者からのフィードバックを基に、メーカー・研究機関・地域が一体となって地域に合った新たな品種・資材や農法を開発するような取り組みを加速させることが重要である。
スマート農業の普及により、データを活用した精密農業が本格化しており、大きなチャンスが到来している。特定の品質を再現性良く達成できると同時に高効率な栽培方法を開発・浸透させることができるかどうかがポイントとなる。
こうして、サプライチェーンを一気通貫でデジタルトランスフォーメーションすることによって、持続可能かつ豊かな農業・食を実現することが可能になる。
前田 佳栄(まえだ・よしえ)さん 1992年、富山県生まれ。2017年、東京大大学院農学生命科学研究科応用生命工学専攻修了(16年度農学生命科学研究科修士課程総代)。学生時代は植物を対象とするバイオテクノロジー関連の研究を行う。実家はカブの契約栽培を行う兼業農家で、夏休みなどに帰省し農作業に汗を流している。現在、日本総研農業チーム所属
(Kyodo Weekly・政経週報 2021年5月3日号掲載)
最新記事
-

米粉代替作戦 小視曽四郎 農政ジャーナリスト 連載「グリーン&ブル...
コメがついに麺にも抜かれた、と総務省調査(2人以上家庭、平均世帯人員2.91人...
-

国産FSC認証広葉樹材を販売 堀内ウッドクラフト
日本森林管理協議会(東京都世田谷区、FSCジャパン)は、木工品製造販売の堀内ウ...
-
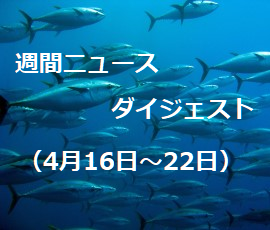
ウクライナ支援で一致 週間ニュースダイジェスト(4月16日~22日)
先進7カ国(G7)農相会合が宮崎市で、2日間の日程で開幕した(4月22日)。ウ...
-

「地域創生」五感で学ぶ 東京農大「食と農」の博物館が企画展
東京農業大学(江口文陽学長)の「食と農」の博物館(東京都世田谷区)は21日、企...
-

漁師さんが「かわいい」と気付いた日 中川めぐみ ウオー代表取締役 ...
水産の世界は物理的な距離よりも、精神的な距離が遠い。水産業界以外の方と、こんな...
-

花粉症対策でスギの伐採加速 週間ニュースダイジェスト(4月9日~15...
政府は首相官邸で花粉症対策を議論する初の関係閣僚会議を開き、岸田文雄首相は6月...
-

2030年に市場規模2100億円へ 食料変えるアグリ・フードテック ...
近年、激化する気候変動などの影響から、世界の食料事情が不安定さを増す中、アグリ...
-

イノベーター養成アカデミー来春開講 社会人も、最短1年で修了 AF...
AFJ日本農業経営大学校(東京都港区、合瀬宏毅校長)は11日、オンラインを活用...
-

施設園芸用モニタ装置を提供 ファーモ、北海道ボールパーク内の施設
スマート農業を推進するIT企業のファーモ(宇都宮市)は、北海道日本ハムファイタ...
-
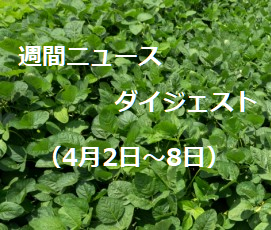
生産拡大と持続可能性の両立を議論へ 週間ニュースダイジェスト(4月2...
気候変動やロシアのウクライナ侵攻で食料の安定供給が世界的な課題となる中、先進7...

 ツイート
ツイート