福祉と農業の連携、高い次元へ 労働力確保から共生社会目指す 共同通信アグリラボ所長 石井勇人
2020.08.13

(写真:ハンディがある人たちがネギの苗を栽培している=埼玉県熊谷市の埼玉福興)
心や体にハンディがあるなど社会的に弱い立場の人々にとって、農場で働く機会が増えてきた。背景には農業分野の労働力不足があるが、多様な個性を受け入れる「共生社会」に対する理解も深まり始めている。
政府は2016年に閣議決定した「ニッポン1億総活躍プラン」に「農福連携の推進」を盛り込み、農林水産業への障害者や高齢者の参加を促すため、19年6月4日に省庁横断の推進会議を開いた。今春策定された農政の中期指針「食料・農業・農村基本計画」も「農福連携」を重要課題に位置付けている。
また、障害者雇用促進法の改正で、働く人のうち一定割合以上を障害者とする「法定雇用率」が18年4月に2.0%から2.2%に引き上げられるなど事業主の責務が強化された。これまで農業とは無縁だった首都圏の企業の中に、特例子会社や農業法人を設立して障害者を雇い入れ、法定雇用率を満たすケースも増えている。
こうした施策を受けて「農福連携」という言葉が定着してきたが、農林水産業が備えている自然との関わりを福祉や医療に役立てる考え方は古今東西からあり、英語ではcare farm(ケアファーム、いたわり合う農場)と呼ぶことが多い。福祉の実践場所として農場を使うという感覚だ。もちろん日本でも同様な取り組みは各地にあり、むしろ行政が「後追い」してきたとも言える。
埼玉県熊谷市でタマネギなど計約6㌶の農場を経営しながら、障がいがある人たちの自立を支援している埼玉福興株式会社も、そうした先駆的な農場の一つだ。 (ソーシャル・ファームを運営する埼玉福興の新井利昌社長)
(ソーシャル・ファームを運営する埼玉福興の新井利昌社長)
1993年、新井利昌社長が19歳だった時に、縫製業を営んでいた父親とともに、障がいのある人の生活寮の運営を始めた。今では心身にハンディがある人だけでなく、刑事事件を起こした障がいがある人や、自立援助ホームなどから身寄りがいない人を受け入れており、看取りまで支援したこともある。18歳~70歳、約30人が大家族のように暮らしていて、新井さんは社長と言うよりはお父さんという存在だ。
農場経営の経験はなかったが、無農薬栽培や水耕栽培の農業に可能性を感じて2004年に農業を事業の中核にした。タマネギの他にネギ、ハクサイ、ホウレンソウなどを、有機栽培を軸に栽培・出荷している。
「農業にはさまざまな作業があるので、それぞれに多様な個性を生かすことができて、皆に居場所がある」と新井さん。根気よく植物を育てる作業に向いている人のために、瀬戸内海の小豆島を訪ねてオリーブの苗を分けてもらい、栽培に挑戦した。16年にオリーブ油の品質を競う国際オリーブコンテンストで金賞を受賞したのが農場の誇りだ。
新井さんは「農福連携よりさらに踏み込んで、小学校なども含めた地域全体が支え合う社会的農場を目指したい」と、農場を「ソーシャル・ファーム」と位置付けている。
農福連携を支援している公益社団法人・日本フィランソロピー協会(東京)は、「喧嘩や逃走もある中で、一緒に生活して地域とともに社会的に自立できる環境を生み出す活動は、誰一人取り残さないというSDGsの理念そのものだ」(高橋陽子理事長)と評価する。
ただ、農福連携の現実としては、労働力の確保としての期待や、法定雇用率の達成といった経営上の判断が先行しがちだ。実際に新型コロナウイルスの感染拡大を受けて今年2月から6月の間に企業などを解雇された障害者数は1104人で、前年同期比152人(16.0%)も増えた。経営悪化で雇用を維持できない企業が増え、求職側も感染リスクや重症化リスクを恐れて活動を控えている可能性がある。
社会や企業の余裕を奪う点でコロナ禍は逆風かもしれないが、多様な個性を組み合わせればみんなが生きやすいという意識が少しずつでも広がり、「地域共生社会」の理念に近づくことを期待したい。(文・写真 共同通信アグリラボ所長 石井勇人)
関連記事:丸の内でJA農福連携マルシェ
最新記事
-

お墓、どうされますか? 藤波匠 日本総合研究所調査部上席主任研究員 ...
出生数減少が止まりません。2015年には100万人以上あった出生数が、7年後の...
-

国産FSC認証広葉樹材を販売 堀内ウッドクラフト
日本森林管理協議会(東京都世田谷区、FSCジャパン)は、木工品製造販売の堀内ウ...
-
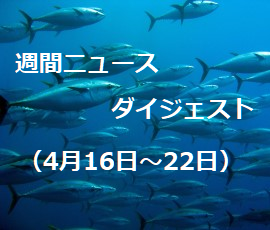
ウクライナ支援で一致 週間ニュースダイジェスト(4月16日~22日)
先進7カ国(G7)農相会合が宮崎市で、2日間の日程で開幕した(4月22日)。ウ...
-

「地域創生」五感で学ぶ 東京農大「食と農」の博物館が企画展
東京農業大学(江口文陽学長)の「食と農」の博物館(東京都世田谷区)は21日、企...
-

健康食品市場9000億円超へ 23年度、ストレス・睡眠・肥満対策で堅...
矢野経済研究所がこのほど発刊した市場調査資料「2023年版 健康食品の市場実態...
-
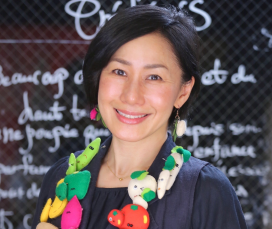
幸福は口福から 安武郁子 食育実践ジャーナリスト 連載「口福の源」
人間の最後まで残る欲の一つである「食欲」(※)。おいしさを味わう幸せ「口福」。...
-

漁師さんが「かわいい」と気付いた日 中川めぐみ ウオー代表取締役 ...
水産の世界は物理的な距離よりも、精神的な距離が遠い。水産業界以外の方と、こんな...
-

花粉症対策でスギの伐採加速 週間ニュースダイジェスト(4月9日~15...
政府は首相官邸で花粉症対策を議論する初の関係閣僚会議を開き、岸田文雄首相は6月...
-

リニューアル、地方進出活発に 動き出した自治体アンテナショップ 畠...
最近、自治体のアンテナショップの移転、リニューアル、新規出店が全国的に活発だ。...
-
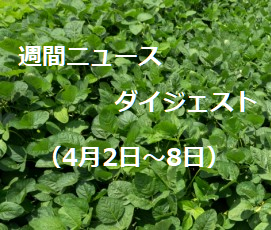
生産拡大と持続可能性の両立を議論へ 週間ニュースダイジェスト(4月2...
気候変動やロシアのウクライナ侵攻で食料の安定供給が世界的な課題となる中、先進7...

 ツイート
ツイート