「時間は等しく流れているのか」 2回目の「震災10年」を考える 山田昌邦 共同通信福島支局長
2021.04.12

「震災10年」を被災地で迎えるのは2回目だ。阪神大震災から10年となった2005年1月は、共同通信神戸支局デスクとして赴任していた。そして今年3月、福島支局で東日本大震災10年に携わることになった。
10年が過ぎても、震災で家族や知人を亡くした悲しみが癒えることのないのは阪神も東日本も変わらないし、自分たちの体験を伝承しようと模索している人たちの姿も重なる。
ただ、福島の被災地を歩くと、「時間は等しく流れているのか」との思いが頭をよぎる。
取り残された風景
震災から10年を経た神戸の街は、復興住宅に住む独居高齢者の孤独死や過大な復興計画などの課題はあったものの、倒壊したビルや住宅地、高速道路はきれいに再建され、少なくとも表面上は〝復興〟を果たしていて、「本当にここで地震があったのか」と思うほどだった。
一方の福島。「復興」という言葉から取り残されたような風景が今なお残る。妨げているのはもちろん、世界最悪ともいわれる事故を起こした東京電力福島第1原発だ。
爆発、破損した原子炉建屋から大量の放射性物質をこの地にまき散らした結果、国の避難指示区域は最大時、沖縄本島とほぼ同じ1150平方㌔㍍に及んだ。除染が進んだ現在も、住民でさえ立ち入りに制限がある「帰還困難区域」が、第1原発が立地する大熊、双葉両町など7市町村にわたって計337平方㌔㍍、猪苗代湖の約3.3倍に相当するエリアで指定されている。
第1原発から約2.5㌔西の帰還困難区域を約14㌔にわたって南北に貫く国道6号は、自動車やバイクは通行できるようになったが、徒歩や自転車では今も通れない。沿道の店舗などは震災後、放置されたままだ。
(写真上:帰還困難区域を縦断する国道6号沿いにあり、震災後、手付かずのままの自動車販売店(福島県富岡町)=3月18日、筆者撮影、以下同)
カジュアル衣料店のショーウインドーには、色あせた10年前の春物ブラウスを着たままのマネキンが立っているし、隣の自動車販売店はガラス張りだった正面が崩落し、店内は吹きさらしの状態。奥の棚には今はもう生産されていない車種のカタログが散乱している。
3月8日に立ち入り規制が一部緩和されたばかりの福島県大熊町の帰還困難区域に入ってみた。当然、道を歩く人は誰一人いない。時折、ウグイスの鳴き声が聞こえる以外、無音の世界だ。玄関脇に、この家の男の子が乗っていたと思われる足踏み式のゴーカートが砂ぼこりをかぶっている。生活感を残したまま、長年の風雨にさらされたり、イノシシなど野生動物に荒らされたりして傷んでいく家々を見ると、胸が詰まる。
手放せない土地
福島県では今も約3万6000人が県内外で避難生活を送っている。
第1原発の南約3㌔に住み、兼業農家だった新長英一さん(72)さんは、津波で自宅が流され、町内の老人保健施設に入所していた妻カツ子さん(68)の両親は、過酷な避難の過程で亡くなった。福島県会津若松市などで避難生活を送った後、5年ほど前に、元の家から約20㌔南の広野町に新築した家に長男(42)と移り住んだ。
「家が流されただけだったら大熊に帰りたかったなぁ。原発事故さえなかったら...」。新長さんは顔をゆがめて言う。
家のあった場所は帰還困難区域になった上、県内各地の除染で生じた土などを埋める「中間貯蔵施設」の用地として、環境省による買収対象になった。「津波で塩をかぶった田畑は売ったが、家があった土地は地上権だけの設定にした。先祖が苦労して手に入れた土地だ。手放すことなんてできねぇっぺさ」
官僚用語
中間貯蔵施設には2015年から除染土が搬入されている。大型ダンプカーで集められた除染土で埋め立てられ、きれいに整地された土地は広大なサッカースタジアムのようだ。東京ドーム約11杯分、計約1400万立方㍍に上る除染土の搬入は来年3月までに終わる予定だが、ここでの貯蔵はあくまで「中間」だ。
搬入開始から30年後の2045年3月には、県外の「最終処分施設」への搬出を完了するのが、国と地元との約束になっている。
しかし搬出先の確保は全くめどが立っていない。「無理だべさぁ。ずっとここに置いたままだ」。新長さんは国の約束を信じていない。
しかも中間貯蔵施設に搬入するのは、帰還困難区域で発生する除染土は計算に入っていない。そもそも同区域全てを除染するのかどうか、国ははっきり考えを示していない。

(各地から集められた除染土が搬入された中間貯蔵施設(福島県大熊町)=2020年12月5日)
菅義偉首相は「たとえ長い年月を経たとしても、帰還困難区域を将来的に必ず解除する方針は変わっていない」としているが、「いつまでに」という期限への言及はない。
何もせずに、数十年かけて放射線量が自然に下がるまで待つのではないか、という疑念も持たざるを得ない。
それでも、この土地への帰還を望んでいる住人は少なくない。そもそも「帰還困難」という言葉自体が国のあいまいな態度を象徴している。「今、帰還は難しいが、将来にわたって不可能とも言っていない」。そんな意味だろう。希望を持っていいのか、決断しなければならないのか。住民の気持ちをもてあそぶような〝官僚用語〟だ。
胃袋から復興支える
一方で、「必ず村に帰る」という意思を貫き、ふるさとの復興を支えている人たちもいる。
第1原発の北西約25㌔の葛尾村。村内唯一の食堂「石井食堂」を営んでいる石井一夫さん(65)一家だ。店は石井さんの妻恵理子さん(61)の両親が昭和30年代に始めた老舗で、昔から盛りがいいことで評判だ。昼時の店内は除染や道路工事の作業員に混じって、村の家族連れも席を埋める。

(福島県葛尾村で唯一の「石井食堂」。大盛りで評判のチャーハンを持つ次男貴裕さん=3月18日撮影)
チャーハンを注文した。長男秀昭さん(36)が運んできたのは、普通の店の3杯分はあろうかという大盛りだ。周りを見回すと、常連客らがそんな料理をペロリと平らげていて、また驚く。
第1原発の事故を受けて村は震災3日後、全村避難を決断。バスに乗せられ、一家は村を後にした。「2、3日もすれば帰ってこられると思っていた」と石井さん。
だが、事故の深刻さが明らかになり、福島市内の体育館や福島県会津坂下町の旅館での避難生活を経て2011年9月、村が役場の出張所を開設した同県三春町の仮設住宅に。商工会議所から頼まれ、仮設商店街に作る食堂を任されることになった。仮設住宅の人たちが集う店だったが、石井さんは「必ず葛尾に戻って店を再開させる」と決めていた。
「総仕上げ」
「生まれ育った土地だから、やっぱり葛尾は気が休まるんだな」。それでも、若い子どもたちにも考えがあるだろうと、村に帰る気があるか聞くと、そろって「一緒に食堂をやる」。2人の息子は調理師学校に進んだ。

(福島県大野町の帰還困難区域に残る住宅。人の営みがなくなり傷みが進む=3月18日)
村の大半で避難指示が解除された翌年の17年7月、元の店の近くで食堂を再開した。震災前約1500人だった村民の1割程度しか当時は帰村していなかった。「うまくいかない」と助言する人もいたが「何とかなるべさ。結果はその時だ」と一家で村に帰るという意思は変わらなかった。
大盛りの温かい食事を提供する石井食堂は、復興に携わる作業員たちを胃袋から支えている。店内には食品や日用品などもそろえ、車が運転できないお年寄りの買い物にも一役買っている。
「今後、復興関連工事も減っていくだろう。先のことは分からないが、いつまでも被災地だと思っていられない。前を向いて進まないと」。石井さんは自らに言い聞かせるように話した。

(福島県大野町の帰還困難区域。解体された住宅跡地にセイタカアワダチゾウの枯れ草。背後にはまだ住宅が残る=3月18日)
震災10年の今年3月11日、東京で政府主催の追悼式が営まれ、菅首相は「福島の本格的な復興・再生、東北復興の総仕上げに全力を尽くす」と式辞で述べた。同様の言い回しは1月の施政方針演説にも出てくる。
「総仕上げ」とは裏腹に、第1原発の廃炉の道筋も、帰還困難区域解除の見通しも、第1原発敷地内にたまり続ける処理水の処分方法も決まっていない。追悼式の5日前、福島県を訪れた首相は「復興は、国がしっかり責任を持って取り組んでいきたい」と述べた。重みを感じさせない言葉である。
(Kyodo Weekly・政経週報 2021年3月22日号掲載)
最新記事
-

お墓、どうされますか? 藤波匠 日本総合研究所調査部上席主任研究員 ...
出生数減少が止まりません。2015年には100万人以上あった出生数が、7年後の...
-

国産FSC認証広葉樹材を販売 堀内ウッドクラフト
日本森林管理協議会(東京都世田谷区、FSCジャパン)は、木工品製造販売の堀内ウ...
-
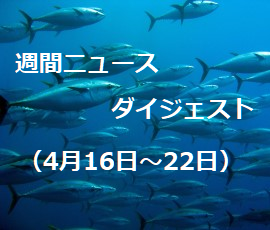
ウクライナ支援で一致 週間ニュースダイジェスト(4月16日~22日)
先進7カ国(G7)農相会合が宮崎市で、2日間の日程で開幕した(4月22日)。ウ...
-

「地域創生」五感で学ぶ 東京農大「食と農」の博物館が企画展
東京農業大学(江口文陽学長)の「食と農」の博物館(東京都世田谷区)は21日、企...
-

健康食品市場9000億円超へ 23年度、ストレス・睡眠・肥満対策で堅...
矢野経済研究所がこのほど発刊した市場調査資料「2023年版 健康食品の市場実態...
-
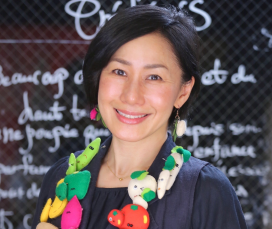
幸福は口福から 安武郁子 食育実践ジャーナリスト 連載「口福の源」
人間の最後まで残る欲の一つである「食欲」(※)。おいしさを味わう幸せ「口福」。...
-

漁師さんが「かわいい」と気付いた日 中川めぐみ ウオー代表取締役 ...
水産の世界は物理的な距離よりも、精神的な距離が遠い。水産業界以外の方と、こんな...
-

花粉症対策でスギの伐採加速 週間ニュースダイジェスト(4月9日~15...
政府は首相官邸で花粉症対策を議論する初の関係閣僚会議を開き、岸田文雄首相は6月...
-

リニューアル、地方進出活発に 動き出した自治体アンテナショップ 畠...
最近、自治体のアンテナショップの移転、リニューアル、新規出店が全国的に活発だ。...
-
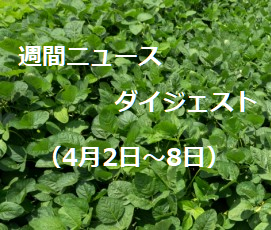
生産拡大と持続可能性の両立を議論へ 週間ニュースダイジェスト(4月2...
気候変動やロシアのウクライナ侵攻で食料の安定供給が世界的な課題となる中、先進7...

 ツイート
ツイート