活発化する水産物の陸上養殖 大企業、ベンチャーが連携
2021.02.08

商社や電力会社などがエビ、サーモンといった水産物の陸上養殖に参入する動きが目立っている。人口増と乱獲により、世界的に水産資源の枯渇が懸念される中、今後の安定供給に寄与するほか、国連が定めた持続可能な開発目標(SDGs)の方向性にも合致していることが背景にある。
水産業の生き残り策
新興国を中心とした食生活の向上や、先進国でのヘルシー志向の高まりも加わって、世界の水産物需要は年々拡大している。海洋汚染をはじめとする環境負荷低減など、SDGsの観点からも、陸上の大型水槽での養殖が今後の安定供給に寄与する手法として期待されている。就業人口の減少や高齢化に直面する日本の水産業の生き残り策としても注目されている。
関西電力は2020年秋、陸上養殖方式での魚介類生産・加工販売事業に参入すると発表した。屋内型エビ生産システム(ISPS)を開発したスタートアップのIMTエンジニアリング(IMTE、新潟県)との共同出資で設立した海幸ゆきのや合同会社(大阪市)がバナメイエビの生産・加工販売事業を行う。
クルマエビに匹敵するうま味を持つバナメイエビを「幸えび」のブランド名で食品加工会社や飲食店などに販売する。このため今後、静岡県磐田市に養殖用プラントを新設する予定で、「22年1月に生産を開始し、22年5月に出荷を開始。以降、年間80㌧程度の生産を予定」している。それまではIMTEが持つプラント(新潟県妙高市)で「年間14㌧程度をOEM(相手先ブランドによる生産)生産する」計画。
IMTEは陸上養殖プラント開発会社で、国との共同研究によって開発された国内唯一の屋内型エビ生産システムを国内外に普及することを目指している。関電は水質・温度・給餌などの管理・制御にモノのインターネット(IoT)、人工知能(AI)、画像解析といったグループが持つDX(デジタルトランスフォーメーション)技術などを活用する。
関電にとってはエネルギー以外の新領域ビジネス創出の一環。現在、輸入が多いバナメイ種の水中を回遊する特性が生かせる生産システムを通じて国内生産を実現し、持続可能な水産業や世界的な水産物需要の高まりにも対応できると判断した。
高速化とスマート養殖
多様な業種の企業がチームを組んで閉鎖循環式陸上養殖を手掛ける動きもある。
NTT、NTT東日本、NTTドコモ、宇部興産、荏原製作所、電通は20年秋、フードテックスタートアップのリージョナルフィッシュ(RF、京都市)と閉鎖循環式陸上養殖システムの構築に乗り出した。(上図)
それぞれがRFと連携協定を結び、水産物の品種改良技術(高速化)とスマート養殖(養殖自動化)を組み合わせた次世代水産養殖システムを開発する。連携に合わせ、NTTドコモ・ベンチャーズ、宇部興産、荏原製作所はRFに出資した。
RFは京大、近畿大などの水産物の品種改良技術シーズをコアとして設立され、オープンイノベーションを通じて、水産物の品種改良技術を持つ。世界のタンパク質不足の解消、日本の水産業再興・地域創生、海洋汚染の防止を目指している。RF産物の品種改良技術により品種改良されたマダイ・トラフグの種苗、飼育ノウハウ、養殖場を提供する。
RFの超高速品種改良に、NTTなど各社がIoT化・AI化により、陸上養殖の水槽で水質環境を見える化・最適化し、生産性を高める養殖「スマート養殖」を組み合わせる。このほか、流体・熱制御などの技術を生かした閉鎖循環式陸上養殖システムの構築、養殖水の浄化や廃棄物の削減・利活用(肥料化・飼料化など)、生育環境制御などの開発やブランディングを担う。
大手商社が相次ぎ事業化へ
大手商社は軒並み、陸上養殖の事業化に意欲的だ。三井物産は17年春、水産物の閉鎖循環式陸上養殖システムを開発したベンチャー、FRDジャパン(さいたま市)に出資、サーモンの陸上養殖事業に参画している。
FRDジャパンは千葉県木更津市の「かずさアカデミアパーク」内にパイロットプラントを建設、「18年8月にパイロットプラントの操業を開始し、19年6月に初出荷した」(三井物産)という。「現在も収穫を継続しており、この結果を踏まえて21年度中の商業プラントへの拡張」(同)を検討している。
三井物産の傘下に入ったFRDジャパンの陸上養殖システムは、バクテリアを利用した高度ろ過技術により、天然海水や地下水を使用せず、人工海水を閉鎖循環させながら水質を維持することが可能。
これにより、従来の陸上養殖で高コストの要因となっていた取水時の水温調節費用や、魚の病気の侵入リスクを大幅に低減させることができるうえ、場所を選ばす、内陸でも養殖を行えるメリットがある。
また、丸紅は20年4月、日本水産と組み、デンマーク企業を子会社化し、サーモンの閉鎖循環式陸上養殖事業に参入、欧州域外での事業展開も視野に入れている。
伊藤忠商事は19年夏、ポーランドの企業グループの日本法人と、日本に閉鎖循環式陸上養殖場を新設し、23年からアトランティックサーモンを国内で販売することで合意している。
(Kyodo Weekly・政経週報 2021年1月25日号掲載)
最新記事
-

米粉代替作戦 小視曽四郎 農政ジャーナリスト 連載「グリーン&ブル...
コメがついに麺にも抜かれた、と総務省調査(2人以上家庭、平均世帯人員2.91人...
-

国産FSC認証広葉樹材を販売 堀内ウッドクラフト
日本森林管理協議会(東京都世田谷区、FSCジャパン)は、木工品製造販売の堀内ウ...
-
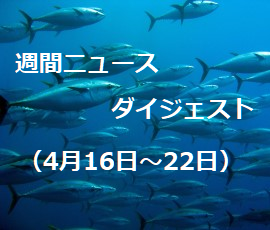
ウクライナ支援で一致 週間ニュースダイジェスト(4月16日~22日)
先進7カ国(G7)農相会合が宮崎市で、2日間の日程で開幕した(4月22日)。ウ...
-

「地域創生」五感で学ぶ 東京農大「食と農」の博物館が企画展
東京農業大学(江口文陽学長)の「食と農」の博物館(東京都世田谷区)は21日、企...
-

漁師さんが「かわいい」と気付いた日 中川めぐみ ウオー代表取締役 ...
水産の世界は物理的な距離よりも、精神的な距離が遠い。水産業界以外の方と、こんな...
-
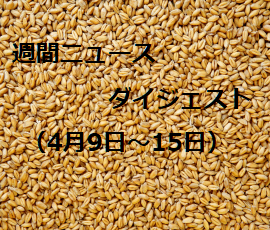
花粉症対策でスギの伐採加速 週間ニュースダイジェスト(4月9日~15...
政府は首相官邸で花粉症対策を議論する初の関係閣僚会議を開き、岸田文雄首相は6月...
-

2030年に市場規模2100億円へ 食料変えるアグリ・フードテック ...
近年、激化する気候変動などの影響から、世界の食料事情が不安定さを増す中、アグリ...
-

イノベーター養成アカデミー来春開講 社会人も、最短1年で修了 AF...
AFJ日本農業経営大学校(東京都港区、合瀬宏毅校長)は11日、オンラインを活用...
-

施設園芸用モニタ装置を提供 ファーモ、北海道ボールパーク内の施設
スマート農業を推進するIT企業のファーモ(宇都宮市)は、北海道日本ハムファイタ...
-
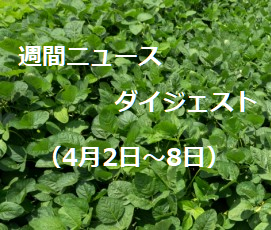
生産拡大と持続可能性の両立を議論へ 週間ニュースダイジェスト(4月2...
気候変動やロシアのウクライナ侵攻で食料の安定供給が世界的な課題となる中、先進7...

 ツイート
ツイート