「本来」を知る大切さ 山下弘太郎 キッコーマン国際食文化研究センター
2020.01.27

「本物の」「本格的な」、と聞くと何やらよさそうに感じませんか。何か価値がありそうな、そんな雰囲気を醸し出しているこれらの形容詞。それはどういうものだと思いますか。
例えば、「本格的な」イタリア料理として出てくるトマトソースのピッツァやパスタはどうでしょう。トマトは南米原産で16世紀になってイタリアに入ってきた新しい食材のはず。
では、それ以前はどうだったかというと、今ではアンチョビとして知られている魚醤(魚を塩漬けにしてその内臓酵素で自家発酵させたもの)が主体だったようです。現存する世界最古のレシピ集といわれる古代ローマ時代の「アピキウスの料理書」(写本)にもガルムという名称でこの魚醤が多用されています。
このガルム、今でもコラトゥーラという名前で南イタリアのアマルフィからシチリアの沿岸部でつくられ、日常の調味料として使われています。そうなるとトマトベースだけが本格的イタリアンというわけではないと気づきます。
(写真は北イタリアの冬の逸品、トリュフパスタ=キッコーマン提供)
もう少し身近な例として、家庭でも居酒屋などでもおなじみのシシャモ。現在流通しているほとんどはカラフトシシャモとも呼ばれるカペリンという魚です。同じサケ目キュウリウオ科なのですが属が違います。しかし、水産庁の魚介類の名称のガイドラインでも標準和名の使用が認められています。となると、われわれが日常、口にしているカラフトシシャモは「本物」ではないのでしょうか。
何やら「本物」とか「本格的」という言葉は使い方が難しいようです。しょうゆに関してはどうでしょう。日本農林規格(JAS)の規定では、しょうゆのつくり方には本醸造、混合醸造、混合の3通りがあります。
本醸造はこうじ菌などの微生物の力で原料を分解、発酵させてつくる方法。混合醸造は同じように発酵過程を経ながら、たんぱく質原料を酸などで分解してつくられるアミノ酸液を加えてつくる方法。混合はあらかじめ協業工場などでつくられた生揚げしょうゆ(加熱処理など製成を施していないもの)を原料にアミノ酸液などを調合してつくる方法、ということになっています。
戦中、戦後の物資不足など日本の近代史の中で派生し定着してきた複数の製造方式はいずれも「本物」とされているわけです。
こうしてみると、「本物」や「本格的」の中身は実は変化するもののようです。なんだか重みがないように感じてしまいますが、そこで重要なのが「本来」を知るということでしょう。郷土料理の研究の中で一つの重要なテーマとなっているのが、各地の歳時食です。おせち料理がその代表ともいえますが、盛り合わせられた一品一品にその地域ならではの思いが込められているのです。
その「本来」の意味があって、使われる食材や調理法に必然性が出てくるのです。高級な食材や見た目の豪華さだけではなく、その料理に込められた「本来」の意味を味わうことが「本物」のおいしさなのかもしれません。
(KyodoWeekly・政経週報 2020年1月27日号掲載)
最新記事
-

米粉代替作戦 小視曽四郎 農政ジャーナリスト 連載「グリーン&ブル...
コメがついに麺にも抜かれた、と総務省調査(2人以上家庭、平均世帯人員2.91人...
-
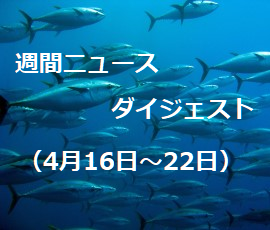
ウクライナ支援で一致 週間ニュースダイジェスト(4月16日~22日)
先進7カ国(G7)農相会合が宮崎市で、2日間の日程で開幕した(4月22日)。ウ...
-

健康食品市場9000億円超へ 23年度、ストレス・睡眠・肥満対策で堅...
矢野経済研究所がこのほど発刊した市場調査資料「2023年版 健康食品の市場実態...
-
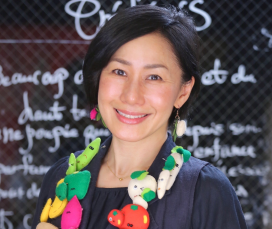
幸福は口福から 安武郁子 食育実践ジャーナリスト 連載「口福の源」
人間の最後まで残る欲の一つである「食欲」(※)。おいしさを味わう幸せ「口福」。...
-

漁師さんが「かわいい」と気付いた日 中川めぐみ ウオー代表取締役 ...
水産の世界は物理的な距離よりも、精神的な距離が遠い。水産業界以外の方と、こんな...
-

花粉症対策でスギの伐採加速 週間ニュースダイジェスト(4月9日~15...
政府は首相官邸で花粉症対策を議論する初の関係閣僚会議を開き、岸田文雄首相は6月...
-

3杯目からうまくなる酒 石鎚酒造、時間かけ作り込む 連載「農大酵母...
日本酒の1回の仕込み量が10㌧を超えるような大型の蔵もあるが、石鎚酒造(愛媛県...
-

2030年に市場規模2100億円へ 食料変えるアグリ・フードテック ...
近年、激化する気候変動などの影響から、世界の食料事情が不安定さを増す中、アグリ...
-

リニューアル、地方進出活発に 動き出した自治体アンテナショップ 畠...
最近、自治体のアンテナショップの移転、リニューアル、新規出店が全国的に活発だ。...
-

福岡から全国区、そして世界へ 一風堂創業の河原成美さん 小川祥平 ...
「とんこつラーメンくさい街」。シンガーソングライターの前野健太さん=埼玉県出身...

 ツイート
ツイート