開発で農業が浸透 変わる狩猟採集社会 連載「アフリカにおける農の現在(いま)」第18回
2021.12.01

狩猟や採集は私たちの祖先が早くからいそしんできた生業で、農耕の開始とともに衰退していったというのが一般的な理解だろう。従って狩猟採集と農耕の両方を行っている人びとの存在は、想像が難しいかもしれない。しかしアフリカの森林地帯などでは、狩猟採集民も農耕を行っている。
これから2回の連載では、狩猟採集民による農業を取り上げる。定住化や自然環境の変化、市場経済の浸透などの影響を受けて変化している狩猟採集社会と農業の関係について紹介する。(写真:農耕民ンジメのラッカセイの収穫を手伝う狩猟採集民バカの女性=手前、カメルーン東部州、2015年9月、関野文子撮影、以下同)
農耕化しても狩猟・採集を継続
「狩猟採集生活」と聞くと、どのような生活を思い浮かべるだろうか。文字通りであれば、狩猟と採集に依拠した生活のことを指す。しかし現在、狩猟採集民と呼ばれる人々の多くは、自然資源に依存した生活だけではなく、小規模な農業や賃金労働など多様で複合的な生業を営んでいる。狩猟採集民に多く共通する特徴として、小集団での移動生活、食物の平等な分配や、社会的な階級がないことなどが挙げられる。
ここでは、定住化や農耕化をしていても狩猟採集活動をなお継続し、上記のような社会的特徴をもつ人々のことを狩猟採集民と呼ぶことにする。彼ら・彼女らが今日でも狩猟採集を生業の中心とし、固有の価値観や社会組織を形作っていることに注目したい。
植物の栽培や家畜の飼育に経済基盤を置く農耕が行われるようになったのは、1万年前のことである。とはいえ、人類の400万年もの歴史の中では、農耕化や産業化はごく最近の出来事で、実に99%以上の期間が狩猟採集生活の時代だったのである。にもかかわらず現在の世界の主な狩猟採集民の人口は、約71万人と推定されており、全人口約72億人(2015年時)のわずか0.01%にすぎず、ごく少数になっている。

(狩猟採集民バカの農耕キャンプ=狩猟採集のため森の中に設置するキャンプのほか、農耕のためのキャンプもある)
遊動的な生活は後退
南北アメリカ、北ユーラシア、アフリカ、南アジア、東南アジア、オーストラリアと、世界各地に狩猟採集民が暮らしている。その中でアフリカには現在も、生業に占める狩猟採集の割合が高い生活を送っている人びとが比較的多くいる。アフリカの主な狩猟採集民として、コンゴ盆地の熱帯雨林を中心に暮らすピグミー系狩猟採集民、南部アフリカの乾燥地帯に暮らすブッシュマン(サン)、東アフリカのハッザが挙げられる。
これらの狩猟採集民は、長らく遊動的な生活をしてきたが、各国の政府の政策などにより、現在は幹線道路沿いの村などへの定住化が進んでいる。加えて、人口増加による狩猟圧の高まりや国立公園の設置によって、自然資源へのアクセスが制限されていることにより、従来の狩猟採集生活の継続が困難になりつつある。
開発による農業の浸透
現在、狩猟採集民にとって農耕化と開発は、切っても切り離せない関係になっている。農耕化とは生業に占める農業の割合が増大し、重要性が相対的に増すことを意味している。近代化論的な見方からすると、狩猟採集民は食物を生産する技術や知識を持たない、経済的に貧しい生活を送る人々とされてきた。そうした近代化の名の下に、定住化や収入向上による生活の改善を目的として、農業などの代替生業の導入による脱狩猟採集民化が図られてきた。
しかし、実際の狩猟採集生活が着の身着のままの不安定な生活かといえば、そうではない。狩猟採集社会では獲物や食料が多くとれたときには、特定の世帯や人物に食物が集中しないよう、食物の分配がされる。村での定住生活が長くなった現在でも、このような食物の分配は継続している。食物の分配は単に食物の不均衡を解消するだけではなく、ともに暮らすメンバー間のコミュニケーションの回路にもなっている。
さらに定住化の進んだ狩猟採集社会でも、移動性が比較的高いことが多く、人間関係の軋轢などがあれば、別の村や定住地以外のキャンプ地に一時的に移住することで、対立の激化を避けようとする。このように狩猟採集民は、自然と共存しながら資源や環境をうまく利用し、豊かな生活文化を築き上げてきた。

(キャッサバやトウモロコシを混作するバカの畑)
開発プロジェクトの影響
それでは、今日の狩猟採集社会に対して、農業はどのような影響を与えているのだろうか。筆者が調査をしてきた狩猟採集民バカが暮らすカメルーン東部州の熱帯雨林地域では、農業関連の開発プロジェクトが数多く実施されている。開発プロジェクトの規模や形態は、農具や種子の配布などの簡単な支援から、農地の拡大と農業の効率化を目指して農業グループを組織するようなものまでさまざまである。
それらのプロジェクトは、バカの経済的安定や農耕民への労働の提供、対価として農作物を受け取るといった、農耕民への依存状態からの脱却を目的に進められている。このような開発プロジェクトの影響が大きい地域では、農耕民に頼ることなく、自らの畑で必要な農作物を完全自給している場合もある。
一方、その他多くのバカは個々の食料の生産や畑の規模などの状況に合わせて、狩猟採集、自給的な小規模農業、農耕民畑での労働を組み合わせながら生活しているのである。
次回は、開発による狩猟採集民の農業の実態や、近隣農耕民との関係について具体的な事例を紹介していく。
関野 文子(せきの・あやこ)京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科アフリカ地域研究専攻
高橋 基樹(たかはし・もとき)京都大学教授、神戸大学名誉教授。京都大学アフリカ地域研究資料センター長。元国際開発学会会長。専門はアフリカ経済開発研究
連載「アフリカにおける農の現在(いま)」では、アフリカの農業と食の現状を、京都大学の高橋基樹教授が若い研究者とともに報告します。
参考文献(第18回)
・尾本恵市 2016『ヒトと文明ー狩猟採集民から現代を見る』筑摩書房
・木村大治・北西功一編 2010『森棲みの生態誌 -アフリカ熱帯林の人・自然・歴史 Ⅰ』京都大学出版会
・木村大治・北西功一編 2010『森棲みの社会誌 -アフリカ熱帯林の人・自然・歴史 Ⅱ』京都大学出版会
・黒田末寿・片山一道・市川光雄編 1987『人類の起源と進化ー自然人類学入門』有斐閣
・二文字屋脩 2020「< 動き> を能う: ポスト狩猟採集民ムラブリにみる遊動民的身構え」『年報 人類学研究』10号 134−154頁
・八塚春名・松浦直毅・亀井伸孝 2013「狩猟採集社会の『復元力と脆弱性』: 第 10 回国際狩猟採集社会会議 (CHaGS10) 参加報告」『アフリカ研究』83号、29-32頁
最新記事
-
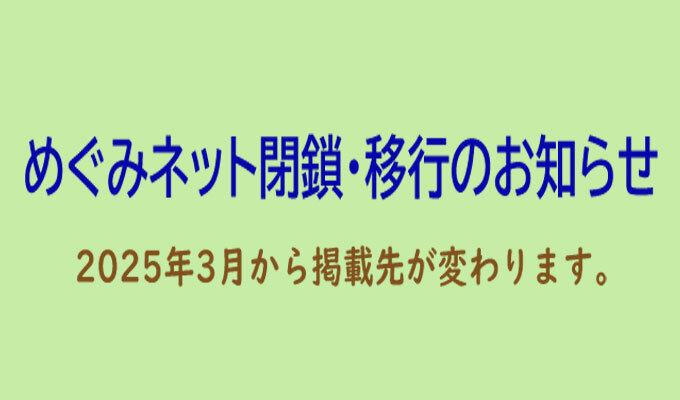
めぐみネット閉鎖・移行のお知らせ
めぐみネットは開設以来、多くの皆さまにご利用いただきましたが、食農分野の情報を...
-

訪日消費、初の8兆円超 週間ニュースダイジェスト(1月12日~1月1...
▼稲作の新たな栽培方法に大賞 高校生ビジネスコンテスト(1月12日) 全国の...
-

豪でも鳥インフル猛威 供給不足で卵の購入制限続く
鳥インフルエンザの感染拡大などによる鶏卵不足から、オーストラリアではスーパーマ...
-

日本食店数3%増で過去最大 タイ 成長は鈍化、総合和食が1位に NN...
日本貿易振興機構(ジェトロ)バンコク事務所は1月8日、タイで営業する日本食レス...
-

食品輸出促進で稼ぐ力強化 週間ニュースダイジェスト(1月5日~1月1...
▼大間マグロに2億円 2番目高値、豊洲で初競り(1月5日) 東京都江東区の豊...
-

コメ交渉の実像伝えず 期待外れの外交文書 アグリラボ編集長コラム
新年を迎えてもコメ相場の高騰が続き、ついに関税を払ってでも米国産を輸入する業者...
-

予算膨張115兆円超え 25年度、歳出・税収最大 週間ニュースダイジ...
▼農業総産出額2年連続増 23年、コメや鶏卵価格上昇(12月24日) 農林水...
-

主食のコメ廃棄に歯止め フィリピン 大統領令準備、年280万人分相当 ...
フィリピン農業省は主食のコメの廃棄に歯止めをかける。年280万人分に相当するこ...
-
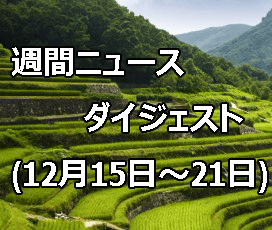
年収の壁123万円決定 手取り増、学生の制限緩和 週間ニュースダイジ...
▼英、TPP加盟が発効 12カ国体制で自由貿易推進(12月15日) 英国の環...
-

高冷地でコメ栽培に挑戦 「有機大国」リヒテンシュタイン
(啓発機構ウェルタッカーの見本農場=ファドゥーツ) 栽培適地とは言えない欧州中...

 ツイート
ツイート