コロナ禍に生かせ「三富新田」 江戸時代から続く循環型農法 長竹孝夫 ジャーナリスト
2020.12.28

「自然回帰」に「地方移住」...こうした現象が各地で起き始めている。田舎に一戸建て物件や山を買い求める。「家族農業」や「小さな農業」も見直されている。コロナ禍社会の一つのあるべき姿を求め、江戸時代から落ち葉堆肥を使った循環型農法を実践する埼玉県南西部の「三富新田」などを歩き、暮らしのヒントを探った。
(写真上:埼玉県三芳町上富地区の短冊状に区切られた地割。遠方には「さいたま新都心」=8月にドローンで撮影、三芳町役場提供)
東京・池袋駅から東武東上線の電車に乗り、約30分で鶴瀬駅。そこから20分ほどバスに揺られ、通称「いも街道」に。目の前に一直線(約2.5㌔)に伸びるケヤキ並木(約250本)は圧巻だ。周囲には大農家や広大な畑が貼りつく。まるで大昔の大規模な「農村地帯」にタイムスリップしたよう。
この三富新田は1694年、川越藩主・柳沢吉保が武蔵野の原野を大規模畑作地として開発した。上富(現・三芳町)、中富(現・所沢市)、下富(同)エリアを総称して三富と呼び、面積は約1400㌶に及ぶ。一戸当たり約5㌶を配分、間口約72㍍、奥行約675㍍の短冊形で、屋敷畑、平地林の地割とした。入植戸数は180戸。今も新田開発の地割は奇跡的に残っている。
三富ブランドのサツマイモ「富の川越いも」のほか、一帯はホウレンソウやサトイモ、ゴボウ、ニンジンなど露地野菜の産地として知られる。2017年に武蔵野地域は「武蔵野の落ち葉堆肥農法」として日本農業遺産に認定され、現在は世界農業遺産承認に向け現地調査中である。三芳町の林伊佐雄町長は「将来に受け継がれるべき伝統的な農業システムである」と胸を張る。
落ち葉を発酵堆肥化
武蔵野は埼玉県南西部から東京中西部に広がる。人と自然とのかかわりを多角的に考察する季刊雑誌「武蔵野樹林」(角川文化振興財団)の「2020夏」で特集され、この中で所沢市下富の農業・横山進さんは「開発っていうと、木を切っていくイメージ。
でも緑を植える開発、木を植える開発が三富の原点。1反(約1000平方㍍)の畑に対し、1反のヤマ(雑木林)の落ち葉を肥料として入れる農業。ヤマは良い空気を出したり、風を防いだり保水したり多面的機能を持っている。木があれば地球環境は持続できる」と強調。

(写真:武蔵野の原風景を残す横山進さん宅の平地林=10月中旬、埼玉県所沢市下富、筆者撮影)
農地土壌に生息する微生物を研究している、DGCテクノロジー・チーフリサーチャーの横山和成さんは「雑木林で毎年作りだされる落ち葉を集め、発酵堆肥化することで常に有機物を供給、農地の生産性を永続させる。そこは生産―消費―再生の無限のサイクルの小さな渦が貼りつく形で、全体として大きな生命圏を形成し、大河の中の無数の水滴を目の当たりにしているようだ」と語っている。
三富新田は、南米チリの砂漠化防止で国際協力機構による技術指導の手本となった。2014年には西アフリカ・セネガルの長官が、環境と経済が調和した村落開発推進計画の一環で視察した。三富新田は日本全国からの視察団も多く「こんな農業が日本にあったのか」と驚きの声が上がるという。
武蔵野は広漠たる野として詠まれた歌枕となっていて「行くすえは空もひとつの武蔵野に草の原より出づる月かげ」(新古今和歌集)は有名な古歌だ。先日、所沢市の武蔵野台地の一角に建築家・隈研吾さんデザインの「角川武蔵野ミュージアム」がオープンした。
1枚70㌔の花こう岩2万枚を手作業で切り出し、積み上げた石の館である。外観は地中から這い上がってきた岩窟や巨大な隕石のようだ。図書、美術、博物が一堂に会する世界初の文化施設で、武蔵野の風土にも合致している。
持続可能な開発目標
武蔵野の魅力を全国に知らしめたのは1898年の国木田独歩の「武蔵野」。「今の武蔵野は林である」と書かれた林はもう都内で発見するのは難しい。今は埼玉の南西部に残されているのみだが、それも乱開発から一部が消失の危機に瀕し、深刻さを増す。
コロナ後の世界について、元埼玉新聞記者でジャーナリストの中西博之さんは「三富新田の循環型農法は環境、社会、経済で調和のとれた社会を目指す国連の持続可能な開発目標(SDGs)と論理は相通じる。コロナ後の社会は持続可能な社会、経済を目指す以外に選択肢はない。三富新田は近世にそれを作っていて持続型社会の未来像を持っている」と話す。
内外のコロナ禍で、私たち日本人は、海外や大都市などに生活の多くを頼れないことを肌で感じた。日用品が手に入らない、業務の内容が変わる、何より人々の不安が増幅した。深刻な新型ウイルスに襲われて、いま新しい生活や生き方が始まろうとしている。
【筆者略歴】ジャーナリスト 長竹 孝夫(ながたけ・たかお) 1953年生まれ。独協大外国語学部ドイツ語学科卒。中日新聞(東京新聞)入社。東京本社社会部(警視庁、都庁、環境省担当)、特別報道部、前橋支局長、社会部次長兼論説委員(総務省、都庁など担当)、校閲部長、編集委員(オピニオン担当)など経て2018年12月退社
(Kyodo Weekly・政経週報 2020年12月14日号掲載)
最新記事
-

米粉代替作戦 小視曽四郎 農政ジャーナリスト 連載「グリーン&ブル...
コメがついに麺にも抜かれた、と総務省調査(2人以上家庭、平均世帯人員2.91人...
-

国産FSC認証広葉樹材を販売 堀内ウッドクラフト
日本森林管理協議会(東京都世田谷区、FSCジャパン)は、木工品製造販売の堀内ウ...
-
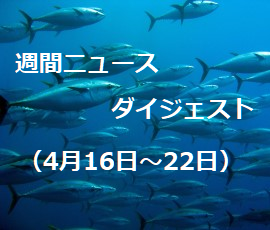
ウクライナ支援で一致 週間ニュースダイジェスト(4月16日~22日)
先進7カ国(G7)農相会合が宮崎市で、2日間の日程で開幕した(4月22日)。ウ...
-

「地域創生」五感で学ぶ 東京農大「食と農」の博物館が企画展
東京農業大学(江口文陽学長)の「食と農」の博物館(東京都世田谷区)は21日、企...
-

漁師さんが「かわいい」と気付いた日 中川めぐみ ウオー代表取締役 ...
水産の世界は物理的な距離よりも、精神的な距離が遠い。水産業界以外の方と、こんな...
-

花粉症対策でスギの伐採加速 週間ニュースダイジェスト(4月9日~15...
政府は首相官邸で花粉症対策を議論する初の関係閣僚会議を開き、岸田文雄首相は6月...
-

2030年に市場規模2100億円へ 食料変えるアグリ・フードテック ...
近年、激化する気候変動などの影響から、世界の食料事情が不安定さを増す中、アグリ...
-

イノベーター養成アカデミー来春開講 社会人も、最短1年で修了 AF...
AFJ日本農業経営大学校(東京都港区、合瀬宏毅校長)は11日、オンラインを活用...
-

施設園芸用モニタ装置を提供 ファーモ、北海道ボールパーク内の施設
スマート農業を推進するIT企業のファーモ(宇都宮市)は、北海道日本ハムファイタ...
-
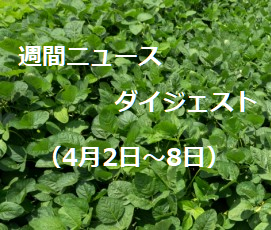
生産拡大と持続可能性の両立を議論へ 週間ニュースダイジェスト(4月2...
気候変動やロシアのウクライナ侵攻で食料の安定供給が世界的な課題となる中、先進7...

 ツイート
ツイート