身近になった「代替肉」 タンパク質が足りなくなる? 畑中三応子 食文化研究家
2020.12.28

いよいよ「代替肉」が身近な食べ物になってきた。「フードテック」という用語も、耳にすることが多くなっている。食(フード)と科学技術(テクノロジー)を合わせた造語である。(上の写真はイメージ)
欧米では先端テクノロジーを駆使した食料生産と食品加工、調理やサービスの開発などが急速に発達している。この分野では立ち遅れていた日本だが、今年4月、農林水産省が「フードテック研究会」を立ち上げ、10月には「フードテック官民協議会」が設立された。フードテックの市場規模は、世界で700兆円に上るといわれる。
フードテックのなかで、日々の食生活に関わりが深いのが、新しいタンパク源として脚光を浴びる代替肉である。
世界人口は77億人から今後30年で20億人増加する見込み。新興国では所得の向上につれて食肉の需要が急増し、日本のような超高齢化社会では、フレイル(加齢による心身の活力低下)を予防して健康寿命を伸ばすために、タンパク質を十分に摂取することがますます必要とされている。そこで近い将来、世界を襲うと予想されるのがタンパク質の不足だ。
畜産には飼料として膨大な量の穀物を必要とするが、これ以上の耕作地の拡大は難しく、温暖化による干ばつや多雨で収量が減る可能性もある。また畜産自体が、温暖化の原因になる二酸化炭素(CO²)とメタンを大量に排出する。
しかも食料生産として、効率がきわめて悪い。牛肉1㌔を生産するには、その10倍以上の穀物を与えなければならず、これが可食部になると、飼料中のタンパク質変換効率は、たったの3%程度になってしまう。
タンパク質危機を解決し、地球温暖化を防止する救世主として現れたのが、代替肉だ。開発をリードするのは米国で、専門企業であるビヨンド・ミート社の設立は2009年と早かった。
少し前までは肉ブームで盛り上がっていた日本だが、「肉食は環境に悪影響を及ぼす」という意識がじわじわと広がりつつあったところに、新型コロナウイルスがきっかけで、環境にやさしい代替肉への関心が急速に高まっている。
プラントベースの代替肉
代替肉には、大きく分けて3種類ある。一つは植物性原料からタンパク質を抽出し、本物そっくりの味・色・香り・食感を作り出したもの。米国では、すでにハンバーガー用のパティやソーセージ、フライドチキン、タコス用ミートなどが浸透している。
先述したビヨンド・ミート社のビヨンドバーガーは、主原料にエンドウ豆を使い、植物油でジューシーさを、ビーツの色素で赤色を出す。ライバル会社であるインポッシブル社のインポッシブルバーガーは大豆濃縮タンパクが主原料で、大豆レグヘモグロビンという物質で風味や食感を出している。タイソン・フーズ、ケロッグなどの大企業も代替肉事業に次々と参入している。
従来の菜食主義者向けの、すりつぶした大豆や豆腐を使ったベジバーガーとは違って、新世代の植物肉バーガーは本物と勘違いするほどの再現性が追求されているのが特徴だ。
こうした植物由来食品には、イデオロギー色の強いベジタリアン、ビーガンの語は使わず、プラントベース(plant based)と表記するのが一般的になった。
今後、植物肉の原料として期待されているのが、藻類。水、光合成に必要な太陽光とわずかな栄養分があれば育ち、成長が速い。中でもタンパク質含有量が多いのがスピルリナで、生産効率は同じ面積で栽培した大豆の20倍と高く、必須アミノ酸とビタミン、ミネラル類も豊富だ。
これからの課題は、肉らしいおいしさをどう作り出すか。海藻を食べ慣れた日本人にとって、親しみのわく代替肉になりそうだ。
もう一つは、動物の細胞を培養したもので、各国で実用化に向けて研究が進められている。当初はハンバーガー1個を作るのに数百万円もかかったが、現在は製造コストが下がり、国内の「細胞農業」ベンチャーのインテグリカルチャー社では、将来的に肉1㌔を200円で作れるという試算を出している。理論上では畜肉だけでなく魚介類も培養できることになり、まさにSFが現実化したようなフードテックだ。
三つ目が、昆虫食。同じ量のタンパク質を生産するのに、必要とする水や飼料が少なく、CO²の排出量も少ない。パウダー状に加工すれば見た目の抵抗感が解消され、欧米ではすでに実用化されている。
特に注目されているのが、味と食感のよいコオロギだ。日本でも無印良品がコオロギせんべいを発売し、なかなかの人気。昆虫を食べる伝統がある日本人には、受け入れやすいかもしれない。
コンビニにも登場
古くは豆腐で野鳥のガンの味に似せたがんもどき、戦後は魚肉ソーセージとカニカマという傑作を生み出した日本は、コピー食品作りの先進国だった。50年代には藻の一種であるクロレラを工業的に大量生産し、人造食料を作るプロジェクトが立ち上がったこともある。
だが、食品の安心と安全性を大切にし、食材にあまり手をかけず、そのものの味を楽しむ日本人が、加工度の高い米国式の代替肉をすんなり受け入れられるだろうか。
肉をたくさん食べるようになったとはいえ、1人当たりの年間消費量は30㌔前後。対して、米国人はおよそ100㌔を食べている。文化的にも、心理的にも、そこまでして肉以外の材料で肉の味を求めるかというと、正直いって、そうは思えない。

(写真:イケアのプラントベース冷凍ミートボールとカップ入りプラントラーメン2種、右下の袋はローソンで販売している大豆ミートのキーマカレー=筆者撮影)
実際、いま出まわっている代替肉の主役は「大豆ミート」である。おもに脱脂大豆を加熱加圧し、特殊な処理で肉のような弾力と繊維質、食感を再現したものだ。今年から急ピッチで外食・中食・内食に普及している。
伊藤ハムは「まるでお肉!」のキャッチフレーズで、カツ、肉団子などの調理済み食品を、大塚食品は「肉じゃないのに、そこそこ美味い!」のキャッチフレーズでハンバーグ、ハム、ソーセージを、マルコメは「ヘルシーを、もっと美味しく」のコンセプトで、そのまま料理に使えるレトルトタイプや冷凍タイプ、総菜の素などの「ダイズラボ」シリーズを展開している。
コンビニでは大豆ミートを用いた総菜、弁当、おにぎり、中華まんが発売され、ファストフードでも大豆由来のパティを挟んだハンバーガーが登場している。ドトールの「全粒粉サンド大豆ミート〜和風トマトのソース〜」や、モスバーガーの「グリーンバーガー」などだ。それぞれ味つけに工夫があり、パティの食感もよく、ボリュームもあって素直においしい。
もともと大豆を「畑の肉」と呼び、大豆由来のタンパク質食品を食べつけている日本人には、肉の代替という問題意識を持たずとも、新しい食品の選択肢として大豆ミートは取り入れやすい。
食べ方が和風中心になる豆腐や納豆、煮豆とは違い、洋風、中華、エスニックに使えるのも大きな利点だ。しかも地球環境に役立ち、自分の健康と美容にも効果大となれば、多くの人が積極的に肉から切り替えるだろう。
しかし、と立ち止まって考える。大豆の国内自給率はたったの6%(2019年度)しかない。いかに環境負荷が畜肉より少なくても、足りない食料は外国から買うという輸入依存は変わらず、素朴に喜ぶ気持ちにはなれないのである。
代替肉が世界で今後さらに普及するとしたら、大豆需要がますます高まって、耕作地を確保するために自然破壊が進み、激しい争奪戦が起こる心配もしてしまう。
さらに、想像する。植物肉なり培養肉なりが、畜肉よりずっと安価に買えるようになったとしたら、所得によって本物を食べる層と、代替肉を食べる層に分かれ、食生活の格差が広がらないだろうか。
地球の健康のため、肉食を減らすのは、正しい道だと思う。だが、その先にはさまざまな多難が待ち構えている。フードテックは、社会と環境の課題を公正に解決することにこそ役立たなくてはならない。
(Kyodo Weekly・政経週報 2020年12月14日号掲載)
最新記事
-

米粉代替作戦 小視曽四郎 農政ジャーナリスト 連載「グリーン&ブル...
コメがついに麺にも抜かれた、と総務省調査(2人以上家庭、平均世帯人員2.91人...
-
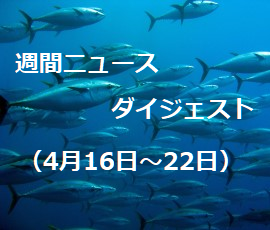
ウクライナ支援で一致 週間ニュースダイジェスト(4月16日~22日)
先進7カ国(G7)農相会合が宮崎市で、2日間の日程で開幕した(4月22日)。ウ...
-

健康食品市場9000億円超へ 23年度、ストレス・睡眠・肥満対策で堅...
矢野経済研究所がこのほど発刊した市場調査資料「2023年版 健康食品の市場実態...
-
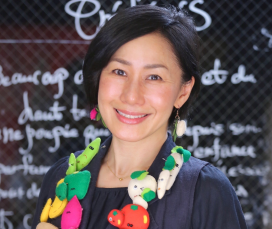
幸福は口福から 安武郁子 食育実践ジャーナリスト 連載「口福の源」
人間の最後まで残る欲の一つである「食欲」(※)。おいしさを味わう幸せ「口福」。...
-

漁師さんが「かわいい」と気付いた日 中川めぐみ ウオー代表取締役 ...
水産の世界は物理的な距離よりも、精神的な距離が遠い。水産業界以外の方と、こんな...
-

花粉症対策でスギの伐採加速 週間ニュースダイジェスト(4月9日~15...
政府は首相官邸で花粉症対策を議論する初の関係閣僚会議を開き、岸田文雄首相は6月...
-

3杯目からうまくなる酒 石鎚酒造、時間かけ作り込む 連載「農大酵母...
日本酒の1回の仕込み量が10㌧を超えるような大型の蔵もあるが、石鎚酒造(愛媛県...
-

2030年に市場規模2100億円へ 食料変えるアグリ・フードテック ...
近年、激化する気候変動などの影響から、世界の食料事情が不安定さを増す中、アグリ...
-

リニューアル、地方進出活発に 動き出した自治体アンテナショップ 畠...
最近、自治体のアンテナショップの移転、リニューアル、新規出店が全国的に活発だ。...
-

福岡から全国区、そして世界へ 一風堂創業の河原成美さん 小川祥平 ...
「とんこつラーメンくさい街」。シンガーソングライターの前野健太さん=埼玉県出身...

 ツイート
ツイート